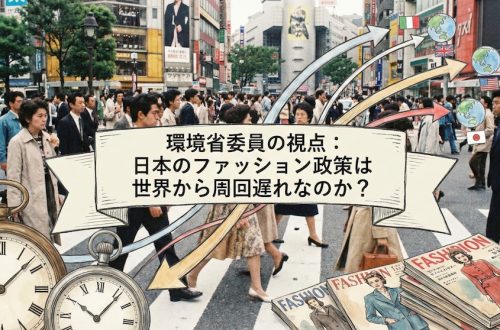執筆者:田中 美穂(株式会社サステナブル・ファッション・ラボ 代表取締役 / 早稲田大学商学学術院 客員研究員)
2025年、サステナビリティへの関心の高まりを背景に、リユースファッション市場はかつてない活況を呈しています。リユース経済新聞社の調査によると、2024年の市場規模は3.3兆円に達し、特に衣料・服飾品とブランド品を合わせたリユースファッション市場は1兆円を超える規模に成長しました。しかし、開業希望者が増加する一方で、「オンラインと実店舗、どちらが本当に儲かるのか?」「どのエリアで開業すべきか?」といった利益構造に関する具体的な情報は不足しているのが現状です。
本記事では、サステナブルファッションの専門家である私が、最新の市場データと国内外の事例を基に、オンライン販売とエリア別実店舗の利益率を徹底比較・分析します。単なる開業ノウハウではなく、データに基づいた事業計画の策定と、これからの時代に求められる「持続可能な古着屋経営」の戦略的視点を提供することで、あなたの成功をサポートします。
【この記事の結論】古着屋の3つの経営スタイル別|特徴と利益の比較
| 経営スタイル | 特徴と利益のポイント |
|---|---|
| オンライン販売 | 初期費用を数十万円に抑えられ、利益を確保しやすい。メルカリShops、BASE、Shopifyなどプラットフォームで手数料が異なり、売上規模に応じた選択が重要。 |
| 実店舗(都心) | 下北沢・高円寺などは集客力があるが、家賃が月37〜52万円と高額。月商200万円以上を目指し、ヴィンテージ品など高単価商品で専門性を出す戦略が必須。 |
| 実店舗(地方・郊外) | 家賃を抑えられ、安定した利益を確保しやすい。課題は集客力のため、オンライン販売との連携(OMO戦略)で全国に顧客を広げることが成功の鍵。 |
目次
【基礎知識】2025年版・古着販売の利益率とその構造
古着販売事業を計画する上で、利益構造の正確な理解は不可欠です。ここではその基礎となる計算方法から、最新の市場動向を踏まえた平均利益率、そして利益を左右する重要要素について解説します。
利益率の計算方法:売上・原価・経費の基本
事業の健全性を測る利益率は、以下の計算式で算出されます。
利益率 (%) = 利益額 ÷ 売上高 × 100
(※利益額 = 売上高 – 原価 – 経費)
各項目を具体的に見ていきましょう。
- 売上高: 商品が売れた金額の総額です。
- 原価(仕入れ値): 商品となる古着を仕入れた際にかかった費用です。古着ビジネスの原価率は、扱う商材にもよりますが平均30%程度と、他の小売業に比べて低い傾向にあります。
- 経費(コスト): 事業運営にかかる費用全般を指します。
- 変動費: 売上に比例して変動する費用(例:オンラインの販売手数料、決済手数料、送料、梱包材費)
- 固定費: 売上に関わらず発生する費用(例:実店舗の家賃、人件費、水道光熱費、オンラインストアの月額利用料)
コンサルティングの現場で散見されるのは、細かな経費の見落としです。例えば、撮影機材やPCの減価償却費、集客のための広告宣伝費、古物商許可の取得費用なども事業経費です。これらを正確に把握し、事業計画に織り込むことが、持続可能な経営の第一歩となります。
2025年現在の古着販売の平均利益率
一般的に古着販売の利益率は30%〜60%が目安とされていますが、これはあくまで参考値です。実際には、扱う商品の特性や販売戦略によって大きく変動します。
- 高利益率が期待できるジャンル: 専門知識を要しますが、希少価値の高いヴィンテージ品や特定のブランド古着は、仕入れ値に対して高い販売価格を設定しやすく、70%以上の利益率も可能です。
- 利益率が変動しやすいジャンル: レギュラー古着(一般的な古着)は、薄利多売の戦略を取ることが多く、利益率は30%〜50%程度に収まる傾向があります。
また、マクロ経済の動向も無視できません。近年の円安は、海外からの仕入れコストを押し上げる要因となっており、利益率を圧迫する可能性があります。国内のリユース市場が拡大を続ける中で、いかに質の高い商品を国内で安定的に仕入れるかという「マテリアルフロー」の最適化が、今後の利益確保において重要な鍵となると考えられます。
利益率を左右する3大要素:仕入れ・価格設定・販売チャネル
利益率を最大化するためには、以下の3つの要素を戦略的に管理する必要があります。
- 仕入れ力: 安定的かつ安価に、魅力的な商品を仕入れる能力は事業の根幹です。国内外の卸業者、一般からの買取、フリーマーケットなど、多様な仕入れルートを開拓することが重要です。
- 価格設定戦略: 相場を把握することは基本ですが、それだけでは価格競争に陥りがちです。私の専門である消費者行動分析の観点から言えば、「顧客がなぜその価格で買うのか」という価値提案が極めて重要です。商品の希少性、背景にあるストーリー、コンディションの良さといった付加価値を的確に伝えることで、相場以上の価格での販売が可能となります。
- 販売チャネルの選定: オンラインか実店舗か、またオンラインの中でもどのプラットフォームを選ぶかによって、手数料や集客コストが大きく異なります。次章以降で詳述しますが、自身の事業コンセプトに最適なチャネルを選ぶことが利益率に直結します。
【徹底比較】オンライン古着販売の利益率分析
オンライン販売は、低コストで始められる手軽さから、多くの新規参入者を集めています。実際にオンラインでの古着屋 開業を目指すための詳細な手順を解説した記事も併せて読むことで、より理解が深まります。ここでは主要なプラットフォームを比較し、その利益構造を分析します。
主要プラットフォーム別手数料と利益率シミュレーション
オンラインで販売する場合、プラットフォームに支払う手数料が利益を大きく左右します。主要なサービスの手数料を比較してみましょう。
表1:主要オンラインプラットフォーム手数料比較(2025年10月時点)
| プラットフォーム | 初期費用 | 月額費用 | 販売手数料 | 特徴 |
|---|---|---|---|---|
| メルカリShops | 0円 | 0円 | 10% | 圧倒的な集客力。メルカリユーザーに直接アプローチ可能。 |
| BASE | 0円 | 0円 or 5,980円 | スタンダード: 6.6%+40円 グロース: 2.9% | 簡単にネットショップを開設可能。デザインの自由度も比較的高め。 |
| Shopify | 0円 | 約5,000円〜 | 2.9%〜3.4%程度 | 世界No.1シェア。拡張性が高く、本格的なブランド構築や海外販売向き。 |
注:手数料はプランや決済方法により変動する場合があります。最新の情報は各公式サイトをご確認ください。
【利益シミュレーション】10,000円の商品が売れた場合の手残り額
- メルカリShops: 10,000円 – 1,000円 (10%) = 9,000円
- BASE (スタンダード): 10,000円 – 660円 (6.6%) – 40円 = 9,300円
- Shopify (ベーシック): 10,000円 – 340円 (3.4%と仮定) = 9,660円 (別途月額費用)
このシミュレーションから、月額費用のかからないメルカリShopsやBASEは初期リスクが低い一方、売上が拡大するとShopifyの方が手数料率では有利になる構造が見て取れます。
オンライン販売のメリット:低固定費がもたらす高い利益率
オンライン販売の最大のメリットは、実店舗にかかる家賃や内装費、人件費といった高額な固定費を大幅に削減できる点です。これにより、特に事業開始初期(スモールスタート)において、売上が不安定な時期でも利益を確保しやすいビジネスモデルと言えます。
オンライン販売のデメリットと対策:送料・広告費・作業コスト
一方で、オンライン特有のコストも存在します。
- 送料: 近年の物流コスト高騰は利益を圧迫します。販売価格に送料を含めるか、別途設定するか、戦略的な判断が求められます。
- 広告費: モール型でない限り、自力での集客が必要です。SNSマーケティングやWeb広告の費用がかかります。
- 作業コスト: 商品撮影、採寸、原稿作成、梱包、発送といった一連の作業は、すべて人件費(時間的コスト)です。
これらのコストを吸収するためには、効率的なオペレーションの構築が不可欠です。例えば、SNSを活用し、広告費をかけずにファンコミュニティを形成する、あるいは撮影や梱包のプロセスを標準化し、時間的コストを削減するといった工夫が利益率の向上に繋がります。
【エリア別】実店舗古着屋の利益率分析
実店舗は、顧客との直接的なコミュニケーションやブランドの世界観を表現できるというオンラインにはない魅力があります。しかし、エリアによってコスト構造が大きく異なるため、慎重な選定が求められます。
都心激戦区(下北沢・高円寺)のコスト構造と利益モデル
下北沢や高円寺は、古着の聖地として知られ、多くの古着好きが集まるため高い集客力が見込めます。しかし、その分家賃相場も高騰しています。
- 家賃相場: 飲食店向け物件情報サイトのデータによると、下北沢駅周辺の平均坪単価は約35,000円、高円寺駅周辺では約25,000円となっています(2025年時点)。仮に15坪の店舗を借りる場合、月々の家賃は下北沢で約52.5万円、高円寺で約37.5万円が目安となります。
- 利益モデル: この高い固定費を賄うためには、高い客単価と回転率が必須です。例えば、家賃50万円、その他経費30万円、原価率40%と仮定すると、月におよそ200万円の売上が必要となります。そのため、ヴィンテージやデザイナーズブランドなど、付加価値の高い商品を揃え、専門性を打ち出す戦略が不可欠です。また、店舗を拠点としたコミュニティ形成やイベント開催により、リピーターを確保することが成功の鍵となります。
地方都市・郊外エリアのコスト構造と利益モデル
地方や郊外では、都心に比べて家賃を大幅に抑えられる点が最大のメリットです。
- コスト構造: 家賃が安い分、固定費を低く抑えられ、損益分岐点を低く設定できます。これにより、都心部ほど高い売上を維持しなくても、安定した利益を確保しやすい構造にあります。
- 利益モデル: 課題は集客です。地域住民をターゲットにした品揃えや、地域密着型のイベント開催で固定客を掴むことが重要です。さらに、私のコンサルティング経験から成功事例として挙げられるのが、オンライン販売との連携(OMO戦略)です。実店舗をショールーム兼オンラインの発送拠点として活用し、全国に顧客を広げることで、地方の地理的デメリットを克服し、安定した収益を上げています。
専門家が分析するエリア選定のチェックリスト
最適なエリア選定のために、私がコンサルティングで用いるフレームワークを基にしたチェックリストを提供します。
- [ ] ターゲット顧客層: あなたがターゲットとする顧客(年齢、性別、ファッションスタイル)は、そのエリアに十分に存在しますか?
- [ ] 競合環境: 周辺にどのような競合店がありますか?(扱うジャンル、価格帯、店舗の雰囲気)差別化は可能ですか?
- [ ] 地域文化: その地域の文化やファッションへの感度は、あなたの店のコンセプトと合致していますか?
- [ ] アクセシビリティ: 最寄り駅からの距離や、周辺の回遊性は集客に影響します。
- [ ] コスト・リターン分析: 想定される家賃と、そのエリアで見込める売上・利益のバランスは取れていますか?
【2025年以降の戦略】サステナビリティを利益に変える方法
これからの古着屋経営において、他社との差別化と利益率向上を実現する上で最も重要なキーワードが「サステナビリティ」です。
なぜ今「サステナビリティ」が付加価値になるのか?
世界のファッション業界は、大量生産・大量消費からの脱却、すなわちサーキュラーエコノミー(循環型経済)への移行を迫られています。この動きは消費者意識にも大きな変化をもたらしました。特にZ世代の環境意識は高く、ある調査では約55%がウルトラファストファッションの環境への悪影響を認識していると回答しています。また、別の調査ではZ世代の約3人に1人がサステナブルファッションを認知しているというデータもあります。
この消費者行動の変化は、「環境や社会に配慮していること」が、商品の価格やデザインと並ぶ強力な購買動機になり得ることを示唆しています。つまり、サステナビリティは単なる社会貢献活動ではなく、事業の付加価値を高め、利益に直結する経営戦略なのです。
利益率を高めるサステナブル戦略3選
私の専門であるサーキュラーエコノミーの視点から、明日からでも実践可能な3つの戦略を提案します。
- アップサイクル商品の開発:
そのままでは販売が難しいダメージ品や売れ残った商品を、リメイクやデザインを加えて新たな価値を持つ「一点物」として蘇らせます。これにより、廃棄コストを削減しつつ、原価の低い商品を高単価で販売することが可能になり、利益率の大幅な向上が期待できます。 - 透明性の高い情報開示(トレーサビリティ):
商品の背景にあるストーリー(例:「このデニムはアメリカの〇〇州で買い付けました」「前の所有者は大切に〇年間着用していました」など)を伝えることで、顧客の共感と愛着を醸成します。これは、価格だけで判断されない強力なブランド価値となり、価格競争からの脱却を可能にします。 - リペア・ケアサービスの提供:
商品を販売するだけでなく、購入後の修理やメンテナンスサービスを提供します。これにより、顧客との長期的な関係性を構築し、LTV(顧客生涯価値)を高めることができます。また、リペアサービス自体が新たな収益源にもなり得ます。
海外事例に学ぶ:成功するサステナブル古着店のビジネスモデル
私のロンドンでの研究経験から見ても、欧米ではサステナビリティを組み込んだリユース事業が既に主流となりつつあります。
- Patagoniaの「Worn Wear」:
アウトドアブランドのパタゴニアは、自社製品の修理サービスや中古品の買取・再販売を行う「Worn Wear」プログラムを展開しています。これは「新品よりもずっといい」という価値観を提唱し、製品のライフサイクルを最大限に伸ばすことで、環境負荷を低減すると同時に、顧客との強いエンゲージメントを構築している好事例です。 - The RealReal:
米国の高級ブランド専門の委託販売サイト「The RealReal」は、専門家による真贋鑑定を付けることで中古品への信頼性を担保し、高級リセール市場を確立しました。委託販売モデルを採用することで在庫リスクを最小限に抑え、サステナブルな消費を促進しながら経済的価値を生み出しています。
これらの事例から学べるのは、環境価値と経済価値は二者択一ではなく、両立可能であるということです。むしろ、これからの時代は環境価値を追求することが、経済的成功の前提条件になると考えられます。
よくある質問(FAQ)
Q: 古着屋開業に必要な初期費用はどれくらいですか?
A: 開業形態によりますが、実店舗の場合は400万円〜600万円程度が目安です。 主な内訳は、物件取得費(保証金・礼金)、内装工事費、初期の仕入れ費用、備品購入費などです。 オンラインストアであれば、これらの費用を大幅に抑え、数十万円から始めることも可能です。
Q: 古着販売に必要な資格や許可はありますか?
A: はい、「古物商許可」が必須です。 これは、中古品を営利目的で売買するために必要な許可で、店舗の所在地を管轄する警察署に申請します。申請から許可が下りるまで約40日程度かかるため、早めの準備が推奨されます。
Q: 利益が出やすい古着のジャンルはありますか?
A: 一概には言えませんが、ヴィンテージ品や特定のブランド古着は、仕入れ値に対して高い価格で販売できる可能性があり、利益率が高くなる傾向があります。ただし、専門知識や目利きが必要となるため、初心者のうちは自分の得意なジャンルや、トレンドのブランドから始めるのがおすすめです。
Q: 「古着屋は儲からない」と聞きますが、本当ですか?
A: 「やり方による」というのが答えです。競争が激しいのは事実ですが、市場自体は拡大しています。成功の鍵は、明確なコンセプト設定、安定した仕入れルートの確保、そしてSNSなどを活用した集客戦略です。 本記事で解説するようなデータに基づいた利益計画と、他店との差別化戦略がなければ、経営は難しくなります。
Q: 未経験からでも古着屋を開業できますか?
A: はい、可能です。しかし、成功のためには古着に関する知識、経営管理、マーケティングのスキルが不可欠です。まずはオンラインで小規模に始める、あるいは古着屋で働くなどして経験を積むことも有効なステップです。
まとめ
本記事では、2025年の古着屋開業を目指す方に向けて、オンライン販売とエリア別実店舗の利益率をデータに基づき徹底比較しました。オンラインは低い固定費で高い利益率を目指せる一方、実店舗はエリア選定と付加価値戦略が成功の鍵を握ります。
重要なのは、単に商品を売るだけでなく、サステナビリティという時代の要請をいかに自社の強みとして利益に繋げるかという視点です。サステナブルファッションの専門家として提言したいのは、これからの古着屋は「循環型経済の担い手」であるという意識を持つべきだということです。この記事で示したデータと戦略が、あなたの開業計画をより現実的で、かつ持続可能なものにする一助となれば幸いです。