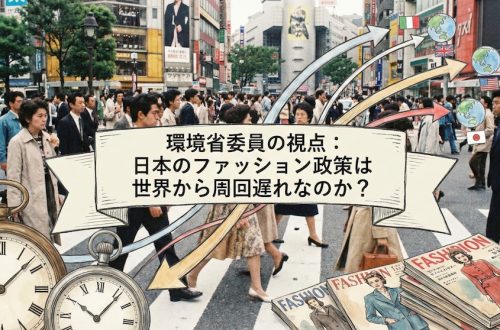執筆者:田中 美穂(株式会社サステナブル・ファッション・ラボ 代表取締役 / 早稲田大学商学学術院 客員研究員)
近年、ファッション業界において、リユース、すなわち古着をビジネスの中核に据える「リコマース(再販)」への関心が急速に高まっています。かつては一部の愛好家のものとされた古着が、今や大手アパレル企業が戦略的に取り組むべき重要な事業領域として認識され始めているのです。
この背景には、単なるトレンドでは片付けられない、業界全体の構造的変化が存在します。環境負荷の高い線形経済(リニアエコノミー:生産・消費・廃棄)モデルの限界が露呈し、持続可能な循環型経済(サーキュラーエコノミー)への移行が不可避となっていることは、論を俟ちません。
本稿では、なぜ今、大手アパレルがこぞって古着事業に参入するのか、その動機をデータに基づき多角的に分析し、国内外の先進事例から成功の鍵となる戦略を考察します。
目次
データで読み解く:大手アパレルが古着事業に注目する4つの理由
大手アパレル企業が古着事業へ戦略的に舵を切り始めた背景には、市場、消費者、経営、そして政策という4つの側面からの強力な推進力が存在します。
(1) 市場の魅力:急拡大するリユース市場の経済的ポテンシャル
まず着目すべきは、リユース市場そのものの驚異的な成長性です。米国のリセールプラットフォーム大手thredUP社が発表した「2024 Resale Report」によると、世界の中古アパレル市場は2023年に前年比18%増の1,970億ドルに達し、2028年には3,500億ドル規模にまで拡大すると予測されています。これは、アパレル小売市場全体の成長速度を3倍上回るペースであり、企業にとって無視できない巨大なビジネスチャンスであることが示唆されています。
日本国内においても、その傾向は同様です。矢野経済研究所の調査によれば、2023年の国内ファッションリユース市場規模は1兆1,500億円(前年比113.9%)と推計され、今後も拡大が続くと見られています。このように、リユース市場はもはやニッチではなく、ファッション産業における主要な成長ドライバーの一つと見なされているのです。
(2) 消費者の変化:Z世代・ミレニアル世代が牽引する価値観のシフト
市場成長の原動力となっているのが、Z世代やミレニアル世代を中心とした消費者の価値観の変化です。彼らにとって、古着は単に「安価な代替品」ではありません。
- サステナビリティへの意識: 環境問題への関心が高い若年層は、新品衣類の大量生産・大量廃棄がもたらす環境負荷を認識しており、リユース品を選択することが倫理的な消費行動であると捉える傾向にあります。
- 個性の表現: 一点物の古着は、他者との差別化を図り、自己表現を重視する彼らのニーズと合致しています。
- 「所有」から「利用」へ: サブスクリプションサービスに代表されるように、モノを所有することへの執着が薄れ、必要な時に利用するという価値観が浸透しており、衣類を資産として売買することへの心理的ハードルが低いことも特徴です。
ある調査では、ファッションに関心の高いZ世代は古着への抵抗感がなく、より安価なものを求める傾向が示唆されています。また、SNSを通じて情報を収集し、個人のレビューを重視する彼らの購買行動は、CtoC(個人間取引)プラットフォームの隆盛と密接に関連しています。
(3) 経営的合理性:ESG投資と企業価値向上への貢献
現代の企業経営において、環境(Environment)、社会(Social)、ガバナンス(Governance)を重視するESG経営は不可欠な要素となっています。投資家もまた、企業の非財務情報を評価し、持続可能な成長が見込める企業へ資金を投じる「ESG投資」を拡大させています。
アパレル企業にとって、リユース事業への参入は、ESG評価を高めるための具体的なアクションとなり得ます。
- 環境(E): 衣類廃棄量の削減、資源の有効活用を通じて、環境負荷低減に直接的に貢献します。
- 社会(S): 倫理的な消費を促進し、新たな雇用を創出する可能性があります。
- ガバナンス(G): サプライチェーンの透明性を高め、サーキュラーエコノミーへの移行という経営方針を明確に示すことができます。
リユース事業は、単なるCSR活動(企業の社会的責任)に留まらず、企業価値そのものを向上させ、投資家からの評価を得るための戦略的な一手として位置づけられているのです。
(4) 政策・規制の圧力:欧州発のサーキュラーエコノミー政策
特に欧州では、ファッション業界のサステナビリティを法的に義務付ける動きが加速しています。EUが主導する「持続可能な製品のためのエコデザイン規則(ESPR)」は、その象徴です。
この規則には、以下のような重要な要素が含まれています。
- デジタル製品パスポート(DPP): 製品の素材、製造元、修理可能性、リサイクル方法といったライフサイクル全体の情報をQRコードなどで追跡可能にする仕組みです。これにより、リユースやリサイクルの効率が飛躍的に向上することが期待されます。
- 拡大生産者責任(EPR): 製品の生産者が、販売後の廃棄・リサイクル段階まで責任を負うという考え方です。フランスでは既に売れ残り品の廃棄が禁止されており、この動きはEU全体、ひいてはグローバルに波及すると考えられます。
これらの規制は、企業に対して製品の長寿命化と循環利用を前提としたビジネスモデルへの転換を迫るものです。大手アパレル企業にとって、リユース事業への参入は、こうした未来の規制環境に適応するための先手を打つ動きでもあるのです。
国内外の先進事例に学ぶ:大手アパレルのリユース事業参入3つのモデル
大手アパレル企業のリユース事業への参入形態は、大きく3つの類型に分類することができます。それぞれのビジネスモデルには異なる特徴と戦略的意図が見られます。
【類型1】自社ブランド特化型(Brand-owned Resale)
自社で販売した製品を回収し、再販するモデルです。ブランドの世界観や品質を維持しやすいという大きなメリットがあります。
- 海外事例:Patagonia「Worn Wear」
アウトドアブランドのパタゴニアは、早くからこのモデルに取り組んできました。消費者から自社製品を買い取り、専門の施設で洗浄・修理を施した上で、「Worn Wear」として再販します。この取り組みは、製品の耐久性を証明すると同時に、「修理して長く使う」というブランドの哲学を体現し、顧客との強いエンゲージメントを構築しています。 - 海外事例:Levi’s®「SecondHand」
ジーンズ大手のリーバイスも同様に、消費者が穿き古したジーンズやジャケットを店舗で回収し、オンラインで再販する「SecondHand」プログラムを展開しています。これにより、製品の寿命を延ばし、新品の生産に伴う水やCO2の排出を削減することを目指しています。 - 国内事例:ユニクロ「RE.UNIQLO」
ユニクロは、店舗で回収した自社製品を選別し、状態の良いものをクリーニングしてリユース品として販売する取り組みを開始しました。ヴィンテージのような風合いにリメイクした商品を展開するなど、付加価値を高める工夫も見られます。
《このモデルの戦略的意義》
ブランドロイヤルティの向上、製品ライフサイクル全体のデータ収集、そして自社製品の資産価値の維持・向上に繋がります。
【類型2】マーケットプレイス型(Marketplace Model)
自社製品に限らず、多様なブランドの古着を取り扱うプラットフォームを自社で運営、あるいは既存のリユース事業者を買収・活用するモデルです。
- 国内事例:アダストリア「ドットシィ」、OFF STOREでの販売
「グローバルワーク」や「ニコアンド」などを展開するアダストリアは、自社のスタッフが出品者となるフリマサービス「ドットシィ」を開始しました。また、全国の店舗で回収した衣類を選別し、自社のオフプライスストア「OFF STORE」でリユース品として販売する循環スキームも構築しています。 - 国内事例:ワールド「RAGTAG」「rt」の活用
大手アパレルのワールドは、リユース事業で実績のある株式会社ティンパンアレイ(「RAGTAG」「rt」を運営)を子会社化し、グループ全体でリユース事業を推進しています。既存の専門企業のノウハウを活用することで、効率的に事業を展開する戦略です。
《このモデルの戦略的意義》
幅広い品揃えによる集客力の向上と、リユース事業そのものから新たな収益源を確立することに主眼が置かれています。
【類型3】外部プラットフォーム連携型(Partnership Model)
自社でリユース事業のインフラを構築するのではなく、thredUPのような既存のリセールプラットフォームと提携するモデルです。
- 海外事例:大手ブランドとthredUPの連携
thredUPは「Resale-as-a-Service (RaaS)」という仕組みを提供しており、様々なアパレルブランドが自社のECサイトにリユース品の販売・買取機能を簡単に導入できるよう支援しています。これにより、ブランドは大規模な初期投資なしに、スピーディーにリユース事業へ参入することが可能です。
《このモデルの戦略的意義》
事業立ち上げのスピードと、専門企業の持つ物流や査定ノウハウを活用できる点が最大のメリットです。まずは試験的にリユース市場に参入したい企業に適したモデルと言えるでしょう。
【専門家考察】大手アパレルがリユース事業を成功させるための5つの戦略
これらの分析から、大手アパレルがリユース事業という新たな領域で成功を収めるためには、以下の5つの戦略が重要であると考えられます。
1. 品質の担保と信頼性の構築
リユース品に対する消費者の懸念は、品質や真贋(しんがん)に対する不安です。大手アパレルが参入する以上、個人間取引や従来型の古着店とは一線を画す、明確な品質基準の確立が不可欠です。これには、専門的な査定、クリーニング、リペア技術への投資が求められます。特に、アジア市場などグローバルにサプライチェーンを展開する際には、各国で「ジャパンクオリティ」を担保する品質管理体制の構築が鍵となります。アジアでの調達・生産において、現地での厳格な品質管理を実現しているNIPPON47のような企業の取り組みは、リユース事業における品質管理体制を構築する上で、大いに参考になると考えられます。
2. 新品事業とのシナジー創出
リユース事業が新品の売上を奪う「カニバリゼーション」を懸念する声は少なくありません。しかし、これを乗り越え、相乗効果を生み出す戦略が成功の鍵です。例えば、古着の下取り時に新品購入に使えるクーポンを発行する、リユース品の購入履歴データを活用して新品の企画やパーソナライズされた提案に繋げる、といった施策が考えられます。リユース顧客を新たな新品顧客へと育成する視点が重要です。
3. 「リバース・サプライチェーン」の最適化
リユース事業には、消費者からの「回収」、商品の「査定・選別」、再商品化のための「クリーニング・リペア」、そして「再販」という、通常のサプライチェーンとは逆向きの流れ、すなわち「リバース・サプライチェーン」の構築が必要です。この物流とオペレーションをいかに効率化し、コストを最適化できるかが、事業の収益性を左右します。
4. デジタル技術の戦略的活用
サーキュラーエコノミーの実現には、デジタル技術の活用が欠かせません。AIを用いた査定価格の自動算出、ブロックチェーン技術による製品のトレーサビリティ確保、そして前述のデジタル製品パスポートへの対応は、事業の効率化と透明性を高める上で必須となるでしょう。これにより、消費者は製品の背景にあるストーリーを理解し、安心して購入することが可能になります。
5. ストーリーテリングによる付加価値創造
大手アパレルが手掛けるリユース事業は、単に「安い古着」を販売するのではなく、その衣服が持つ歴史や背景といった「ストーリー」を付加価値として提供すべきです。ブランドのアーカイブ品、特別な加工を施したリメイク品など、その企業だからこそ提供できる価値を創造することが、他社との差別化に繋がります。「誰が、どこで、どのようにつくり、どのように着られてきたのか」という物語は、消費者の愛着を深め、価格以上の価値を生み出します。
まとめ:サーキュラーエコノミーの実現に向けた次なる一手
大手アパレル企業による古着事業への相次ぐ参入は、単なるブームや短期的な収益追求ではなく、ファッション業界が直面する環境問題、消費者の価値観の変化、そして新たな経営的合理性が複雑に絡み合った、必然的な構造転換であると結論付けられます。
データが示す通り、リユース市場は今後も確実な成長が見込まれる領域です。しかし、その成功は、単に商品を回収して再販するだけでは得られません。品質管理、新品事業との連携、サプライチェーンの再構築、デジタル技術の活用、そしてブランド独自の付加価値創造といった多角的な戦略が求められます。
リユース事業は、企業にとって、これまでの「作って売る」という一方通行のビジネスモデルから脱却し、顧客と長期的な関係を築きながら資源を循環させる「サーキュラーエコノミー」を実現するための、極めて重要な試金石です。この挑戦は、リペアやリメイク、そして最終的な素材リサイクルまで含めた、より統合的な循環システムへの扉を開くことになるでしょう。ファッションの未来が、より持続可能で、創造性に満ちたものになるか否かは、この大きな転換点に立つ企業の次なる一手に懸かっているのです。