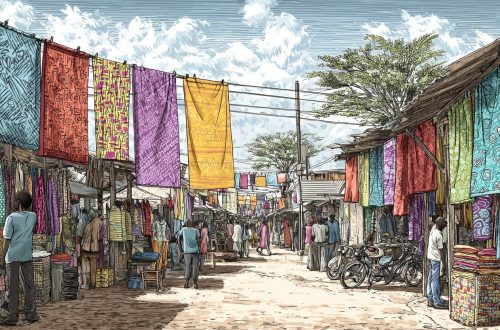執筆者:田中 美穂(株式会社サステナブル・ファッション・ラボ 代表取締役 / 早稲田大学商学学術院 客員研究員)
近年、ファッション業界におけるサーキュラーエコノミーへの移行は、欧米を中心に語られることが多い潮流でした。しかし、そのマテリアルフロー(物質循環)をグローバルな視点で捉えたとき、アジアが持つ巨大なポテンシャルと複雑なダイナミズムを見過ごすことはできません。特に、リユースファッション市場の急成長は目覚ましく、その最前線で何が起きているのかを肌で感じるため、私は先日、韓国・ソウルへと飛びました。
今回の目的地は、眠らない街として知られる東大門(トンデムン)。観光客向けの華やかなショッピングモール群の裏側で、深夜から明け方にかけてプロのバイヤーたちが集う卸売市場が存在します。中でも、古着を専門に扱うマーケットは、アジアにおけるリユースファッションのサプライチェーンを理解する上で、極めて重要な示唆を与えてくれる場所です。
本稿では、深夜の東大門古着マーケットの現地調査から見えてきた熱狂と、その裏側に潜む構造的課題、そして日本市場がそこから何を学ぶべきかについて、データと実地調査を交えながら考察してまいります。
目次
データで見る韓国リユース市場のポテンシャルとアジアの地殻変動
まず、韓国のリユース市場が現在どのような位置にあるのか、マクロな視点から確認しておきましょう。
急拡大する韓国のセカンドハンド市場
韓国のセカンドハンド市場(中古品市場)は、近年驚異的な速度で成長しています。韓国インターネット振興院(KISA)の調査によると、2008年に約4兆ウォンだった市場規模は、2021年には24兆ウォン(約2.5兆円)へと6倍に拡大しました。さらに、同機関は2025年までに市場が43兆ウォン(約4.5兆円)に達すると予測しており、その成長ポテンシャルの高さがうかがえます。
この成長を牽引しているのは、環境意識の高い若年層と、eコマース技術の進化です。デジタルネイティブである彼らは、オンラインプラットフォームを駆使して手軽に古着を売買し、サステナブルな消費をライフスタイルの一部として取り入れています。この消費者行動の変化が、リユース市場全体の底上げに繋がっていると考えられます。
日本市場との比較分析
日本のリユース市場もまた成長軌道にあります。2023年の国内ファッションリユース市場規模は1兆1,500億円と推計され、2024年には1兆2,800億円に達する見込みです。市場規模自体は日本が大きいものの、成長率やデジタルプラットフォームの活用度においては、韓国市場から学ぶべき点は少なくありません。
【表1】日韓リユースファッション市場の比較
| 項目 | 韓国 | 日本 |
|---|---|---|
| 市場規模(2025年予測) | 約4.5兆円(全中古品) | 約4兆円(全中古品) |
| 成長ドライバー | 若年層の環境意識、オンラインプラットフォームの進化 | サステナブル意識、フリマアプリの普及 |
| 特徴 | スピード感のある卸売市場、K-POPカルチャーとの連動 | ヴィンテージ文化の深化、品質へのこだわり |
| 主要プレイヤー | Danggeun Market, Bungaejangter等のC2Cアプリ | セカンドストリート、メルカリ、ZOZOUSED等 |
出典:各種報道・調査レポートを基に筆者作成
特筆すべきは、韓国における「卸売市場」の存在です。東大門のような巨大なハブが、国内だけでなくアジア全域のマテリアルフローを支える結節点として機能している点は、日本の市場構造と大きく異なります。
アジアにおける古着ハブとしての韓国
近年、欧米の良質なヴィンテージ古着が枯渇傾向にある中、世界のバイヤーは新たな供給地としてアジアに注目しています。タイがその筆頭として挙げられることが多いですが、韓国もまた、日本や中国、欧米から大量の古着が集まり、選別・再流通されるハブとしての機能を強めています。東大門の深夜マーケットは、まさにそのダイナミズムを象徴する現場と言えるでしょう。
【現地レポート】深夜に躍動する東大門古着マーケットの熱狂
私が東大門に到着したのは、日付が変わろうとする午後11時過ぎ。doota!などの大型ファッションビルが徐々に静けさを取り戻す中、その裏通りにある卸売ビル群は、これからが本番といった様相を呈していました。
喧騒とエネルギー:五感で捉えるマーケットの情景
私が主に調査したのは、「光熙市場(クァンヒシジャン)」や「東平和市場(トンピョンファシジャン)」といった、卸売専門のファッションビルです。深夜2時、ビルの中は人とモノの熱気でむせ返るようでした。狭い通路を、巨大なビニール袋に詰め込まれた衣類の山を運ぶ人々が絶え間なく行き交います。
- 視覚: 天井までうず高く積まれた古着のベール(圧縮梱包された塊)。様々な言語で書かれたタグ。真剣な眼差しで商品を吟味するバイヤーたち。
- 聴覚: 韓国語、中国語、英語が飛び交う喧騒。ビニール袋が擦れる音、台車が床を滑る音、そして電卓を叩く音。
- 嗅覚: 古着特有の匂いと、それを打ち消すかのような柔軟剤の香り。そして、夜食の屋台から漂う香ばしい匂い。
そこは、単なる売買の場ではなく、グローバルなサプライチェーンの末端が凝縮された、生々しいエネルギーに満ちた空間でした。
グローバルなマテリアルフローの縮図
山積みにされた古着のベールには、どこから来たのかを示すラベルが貼られています。「USA」「JAPAN」「UK」—。先進国で消費された衣類が、コンテナ単位で韓国に輸入され、この場所で解体・選別され、新たな価値を与えられていくプロセスが可視化されています。
ある店舗の店主は、「日本の古着は品質が良いから人気が高い。特にアウトドアブランドやキャラクターものは、すぐに売れていく」と話してくれました。ここで選別された衣類は、韓国国内の小売店だけでなく、東南アジアや中東、アフリカ諸国へと再び輸出されていきます。まさに、サーキュラーエコノミーにおける「マテリアルフロー」の巨大な中継地点なのです。
バイヤーたちの真剣勝負:ビジネスの最前線
マーケットの主役は、国内外から集まるプロのバイヤーたちです。彼らは懐中電灯を片手に、ベールの中から宝物を探し出すように、一枚一枚のコンディションやブランド、デザインを瞬時に見極めていきます。
- 選別: 驚くべきスピードで衣類を仕分け、購入する「山」と見送る「山」に分けていきます。
- 交渉: 店主との価格交渉は、電卓を介して行われることがほとんど。最低購入ロット数が決められている店舗も多く、個人客を相手にしない卸売ならではの光景が広がります。
- 物流: 交渉が成立すると、商品はその場で巨大な袋に詰められ、配送業者の手で韓国全土、あるいは港へと運ばれていきます。
この一連の流れは極めてシステマティックであり、深夜から早朝という限られた時間の中で、膨大な量の衣類が取引されていました。このスピード感と効率性こそが、東大門マーケットの競争力の源泉であると強く感じました。
熱狂の裏側にある構造的課題とサステナビリティへの問い
しかし、この熱狂的なビジネスの裏側には、サステナブルファッション研究者として看過できない、いくつかの構造的な課題が存在することも事実です。
サプライチェーンの不透明性という課題
東大門に集まる古着が、具体的にどのような経路で、誰の手によって集められたのか。そのトレーサビリティは極めて不透明です。先進国で寄付された衣類が、意図せず商業ルートに乗り、最終的に利益を生む商品として取引されているケースも少なくないと考えられます。これは、善意の寄付が引き起こす「ウェイスト・コロニアリズム(廃棄物の植民地主義)」の問題とも関連し、サーキュラーエコノミーを推進する上で避けては通れない論点です。
品質管理とトレーサビリティの重要性
マーケットで取引される古着は、文字通り玉石混交です。中には高品質なヴィンテージ品もあれば、再販が困難なほど傷んだ衣類も混在しています。選別はバイヤー個人の目利きに大きく依存しており、標準化された品質基準は存在しません。
この点は、消費者に安心・安全なリユース品を届けるという観点から、大きな課題と言えるでしょう。ライフサイクルアセスメント(LCA)の観点からも、一度市場に出た製品の品質をいかに維持し、その価値を最大化するかは、環境負荷削減の鍵となります。
労働環境への視点:サーキュラーエコノミーにおける「S (Social)」の側面
深夜から早朝にかけて、重い荷物を運び続ける労働者たちの姿も目の当たりにしました。ESG投資が重視される現代において、環境(E)だけでなく、社会(S)やガバナンス(G)への配慮は不可欠です。サーキュラーエコノミーの担い手である人々の労働環境が、公正かつ安全であるかという視点も、今後より一層重要になると考えられます。
日本市場への示唆と今後の展望
東大門の深夜古着マーケットでの調査は、日本のリユースファッション業界が今後、アジア、そして世界のサーキュラーエコノミーの中でどのような役割を果たしていくべきかを考える上で、多くの示唆を与えてくれました。
韓国モデルから学ぶべき「スピード感」と「集積の力」
東大門が持つ、圧倒的な物量とスピード感、そして関連業種が集積することで生まれる効率性は、日本の市場が学ぶべき点です。個店が点在する日本の構造とは異なり、巨大なハブ機能を持つことで、国内外の需要をダイナミックに取り込み、ビジネスをスケールさせています。
品質基準の確立と「ジャパンクオリティ」の可能性
一方で、日本の強みは、その品質管理能力にあると考えられます。サプライチェーンの透明性を確保し、厳格な品質基準を設けることは、韓国モデルとの差別化を図る上で極めて重要です。例えば、アジア市場での調達において、現地での品質管理を徹底し、ジャパンクオリティを実現している企業の取り組みは、業界全体の品質向上に大きく寄与する可能性を秘めています。消費者が安心して購入できる信頼性の高いリユース品を供給する体制の構築は、日本がアジア市場でリーダーシップを発揮するための鍵となるでしょう。
アジアのハブを目指すための戦略的視点
日本は地理的にも、アジアにおけるリユースファッションのハブとなるポテンシャルを十分に持っています。国内で回収された質の高い古着を、適切な品質管理とトレーサビリティ情報を付与した上で、アジア市場に供給していく。あるいは、アジア各国から集めた古着を日本で高度に選別・リペアし、付加価値を高めて再流通させる。こうした戦略的視点が、今後の成長には不可欠です。
まとめ:熱狂の先にある、持続可能な未来へ
ソウル・東大門の深夜古着マーケットは、リユースファッションが持つ爆発的なエネルギーと、グローバルなサーキュラーエコノミーのリアルな姿を私に示してくれました。そこには、効率性とスピード感を追求したダイナミックなビジネスモデルが存在する一方で、透明性や品質管理、労働環境といったサステナビリティにおける重要な課題も内包されています。
この熱狂を単なるブームで終わらせず、持続可能なシステムへと昇華させていくためには、私たちステークホルダー一人ひとりの努力が求められます。企業はサプライチェーンの透明化と品質基準の確立に努め、消費者は製品の背景にあるストーリーに関心を持つ。そして研究者である私は、データと実地調査に基づいた客観的な分析を通じて、その道筋を照らし続けていきたいと考えています。
アジアのリユースファッション市場は、まさに今、大きな転換期を迎えています。東大門の喧騒の中で垣間見た未来の可能性を、日本の、そして世界の持続可能なファッションへと繋げていくこと。それが、今回の調査を経て、私が改めて強く抱いた使命感です。