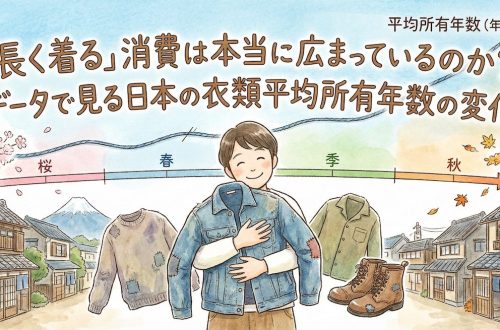執筆者:田中 美穂(株式会社サステナブル・ファッション・ラボ 代表取締役 / 早稲田大学商学学術院 客員研究員)
近年、サステナビリティへの関心の高まりを背景に、リユースファッション市場が世界的に拡大しています。リユース経済新聞の調査によると、2024年の国内リユース市場規模は3.3兆円に達し、15年連続で成長を続けています。特に衣料・服飾品とブランド品を合わせたファッション領域は1兆円規模にまで拡大しており、多くの人々にとって古着が身近な選択肢となっていることが示唆されています。
しかし、その選択理由が「安いから」という一点に留まってはいないでしょうか。価格という経済的メリットはリユースの魅力の一つですが、それは数多ある価値の側面に過ぎません。
本稿では、サステナブルファッション研究者として、リユース、すなわち古着が持つ価値を「環境」「経済」「文化」「社会」という4つの側面から多角的に解き明かします。最新のデータや国際的な事例を基に、一着の古着が秘める本質的な価値を問い直し、皆さんのファッション選びに新たな視点を提供することを目指します。この記事を読めば、あなたのクローゼットがより豊かで持続可能な未来へと繋がる第一歩となるでしょう。
【この記事の結論】リユース服の価値は「安さ」だけではない
リユース服(古着)を選ぶことは、単なる節約以上の4つの本質的な価値を持つ、賢明でサステナブルな選択です。
- 環境価値:新品の服が持つ環境負荷を大幅に削減
新品のTシャツ1枚には水約2,700リットル、CO2約25.5kgもの環境負荷がかかります。古着を選ぶことで、これらの製造プロセスを省略し、地球環境への貢献が可能です。- 経済価値:高品質な服を賢く手に入れ、新たな市場を創出
過去の高品質な製品を手頃な価格で入手できるだけでなく、リユース市場の成長は鑑定士やリペア職人など新たな雇用を生み出しています。- 文化・社会的価値:「一点物」が持つ物語と自己表現を楽しむ
ヴィンテージ品にはその時代を映す物語があり、誰とも被らない一着は個性的な自己表現を可能にします。また、寄付を通じて社会貢献にも繋がります。- 新しい消費行動:リセールバリュー(再販価値)を意識する
将来売ることを前提に価値が落ちにくい服を選ぶことは、衝動買いを減らし、一着を大切にするサステナブルな消費スタイルに繋がります。
目次
なぜ古着は安いのか?価格の背景にある経済メカニズム
多くの人が抱く「古着はなぜ安いのか?」という疑問。その答えは、現代のファッション産業が抱える構造的な課題と、リユース市場独自の流通システムにあります。
大量生産・大量消費社会が生み出す供給過多
現代のファッション業界、特にファストファッションは、短いサイクルで大量に商品を生産・販売するビジネスモデルを主流としてきました。世界の衣料品製造量は2000年から2014年の間に約2倍に増加した一方で、衣類の平均着用回数は減少傾向にあります。この「作りすぎ」と「着なさすぎ」が、マテリアルフロー(物質の流れ)の観点から見ると、一次市場(新品市場)から二次市場(リユース市場)への膨大な衣類の流入を生み出しています。
供給が需要を上回れば価格が下がるのは経済の基本原則です。リユース市場における価格設定の根底には、この供給過多という構造的な要因が存在していると考えられます。
流通コストの最適化と多様な仕入れルート
リユース市場の価格競争力を支えるもう一つの要因は、最適化された流通コストです。新品の衣類とは異なり、古着は以下のような多様なルートで仕入れられます。
- 個人からの買取: 消費者が店舗や宅配サービスを利用して直接売却する。
- 事業者からの買取: アパレル企業の余剰在庫やサンプル品などを引き取る。
- 海外からの輸入: アメリカやヨーロッパなどからコンテナ単位で大量に輸入する「ベール」と呼ばれる古着の塊。
これらのルートは、新品の複雑なサプライチェーンに比べて中間マージンが少なく、企画・製造コストもかからないため、販売価格を抑えることが可能になります。私が以前在籍していた商社での経験からも、国内外の効率的な物流網の構築が、リユースビジネスの経済合理性を高める上で極めて重要であると分析しています。
「価格」だけでは測れない「価値」の存在
しかし、すべての古着が「安い」わけではありません。特定の年代に製造され、歴史的・文化的価値を持つ「ヴィンテージ品」は、時に新品以上の高値で取引されます。例えば、特定の年代のデニムジャケットや、今はなきブランドのアーカイブ作品などは、希少性から資産としての価値を持つことさえあります。
このように、リユースファッションの価格は二極化しており、「安い」という側面だけでその価値を判断することはできません。この価格の背景にある、より本質的な価値について、次章から掘り下げていきましょう。
【環境的価値】ライフサイクルアセスメント(LCA)で見る一着のインパクト
「古着は環境に良い」という言葉はよく耳にしますが、その効果は具体的にどの程度なのでしょうか。私の専門分野であるライフサイクルアセスメント(LCA)の手法を用いて、そのインパクトを定量的に見ていきましょう。
新品の服一着が環境に与える負荷とは
LCAとは、製品の原料調達から製造、使用、廃棄に至るまでの全段階(ライフサイクル)における環境負荷を科学的・定量的に評価する手法です。これを用いて、例えばごく一般的なコットンTシャツ一着の環境負荷を見てみると、驚くべき事実が浮かび上がります。
- 水消費量: 約2,700リットル。これは、一人の人間が約2年半で飲む水の量に相当すると言われています。
- CO2排出量: 約25.5kg。これは、500mlペットボトル約255本を製造する量に匹敵するとも試算されています。
特に、原料である綿花の栽培や生地の染色工程で、水資源の消費と水質汚染が集中することが研究で示されています。
| 環境負荷項目 | Tシャツ一着あたりのインパクト(目安) |
|---|---|
| 水消費量 | 約2,700リットル |
| CO2排出量 | 約25.5kg |
(出典:WWF、環境省などのデータを基に作成)
古着を選ぶことで削減できる環境負荷の定量評価
では、新品の代わりに古着を一着選ぶと、どれだけの環境負荷を削減できるのでしょうか。古着は、この製造プロセス全体をスキップできるため、その削減効果は絶大です。
ある研究では、新品の衣類を代替して古着を利用した場合の環境負荷削減効果が分析されています。新品の製造にかかる膨大な水やエネルギー、CO2排出をほぼゼロにできると考えると、古着を選ぶという個人の小さな選択が、地球環境に与えるポジティブなインパクトは計り知れません。「環境に良い」という漠然としたイメージは、LCAの視点で見ると、これほど明確な数値として示されるのです。
欧州の先進事例に学ぶ、サーキュラーエコノミーの可能性
サステナブルファッションの分野では、欧州が先進的な取り組みを進めています。特に注目すべきは、フランスで2022年1月から施行された「売れ残り品の廃棄禁止法」です。これは、アパレル企業が新品の売れ残り商品を焼却・埋め立てすることを禁じ、寄付やリサイクルを義務付ける画期的な法律です。
さらに欧州連合(EU)全体でも、2025年までに繊維製品の分別収集を義務化するなど、サーキュラーエコノミー(循環型経済)への移行を加速させる政策が次々と打ち出されています。これらの動きは、リユースを単なる消費者の選択肢から、社会システム全体で推進すべき重要な戦略と位置づけていることを示しています。日本が今後、真に持続可能なファッション産業を構築する上で、欧州の事例から学ぶべき点は非常に多いと考えられます。
【経済的価値】賢い消費と新たな市場の創出
リユースファッションは、環境だけでなく経済的な側面からも大きな価値を持っています。それは消費者個人にとってのメリットに留まらず、新たな市場や雇用を創出する原動力ともなっています。
消費者にとっての経済的メリット:高品質と低価格の両立
古着の魅力は、単に「安い」ことだけではありません。むしろ、「過去の高品質な製品を手頃な価格で入手できる」点にこそ、その経済的価値の本質があります。
特に、ファストファッションが主流になる以前の製品は、現代の同価格帯の新品と比較して、より上質な素材や丁寧な縫製が施されているケースが少なくありません。賢い消費者にとって、リユース市場は、流行に左右されない普遍的なデザインと耐久性を兼ね備えた衣類を、合理的な価格で見つけ出すための宝庫と言えるでしょう。
成長を続けるリユース市場と新たな雇用
前述の通り、国内外のリユース市場は著しい成長を続けています。この市場の拡大は、経済全体にポジティブな影響を与えています。
- 新たな雇用の創出: 買い取った衣類を査定する鑑定士、商品を修繕するリペア職人、オンラインプラットフォームを運営するITエンジニアやマーケターなど、リユース市場は多様な専門職を生み出しています。
- 地域経済の活性化: 地域に根差したリユースショップは、コミュニティの交流拠点としての役割も担い、地域内での経済循環を促進します。
私のコンサルティング経験においても、多くの企業がこの成長市場に新たなビジネスチャンスを見出しており、リユースは循環型経済を牽引する重要な産業セクターとして確立されつつあると分析しています。
リセールバリューを意識した新しい服の選び方
リユース市場の成熟は、私たちの消費行動にも新たな視点をもたらします。それが「リセールバリュー(再販価値)」を意識した服の選び方です。
これは、将来的に売却することを前提に、購入時から資産価値が落ちにくいブランドやアイテムを選択するという考え方です。例えば、普遍的なデザインを持つ高級ブランドの定番品や、希少性の高いコラボレーションアイテムなどは、中古市場でも高い価格で取引される傾向にあります。
このアプローチは、衝動買いを減らし、一着一着を大切に扱う意識を高めることにも繋がります。これは、環境・社会・ガバナンスを重視するESG投資の考え方にも通じる、極めて現代的でサステナブルな消費スタイルと言えるでしょう。
【文化的・社会的価値】一着が紡ぐ物語と多様性の尊重
リユースファッションの価値は、環境や経済といった合理的な側面だけでは語り尽くせません。一着の古着には、時代を越えて受け継がれる物語があり、私たちの社会をより豊かにする文化的な力と社会的な意義が宿っています。
時代を映す鏡としてのヴィンテージファッション
ヴィンテージファッションは、単なる「古い服」ではありません。それは、デザイン、素材、縫製技術、そしてその服が着られていた時代の空気感までをも伝える、生きた歴史的資料です。
例えば、70年代のベルボトムジーンズは当時のカウンターカルチャーを象徴し、80年代のパワースーツは女性の社会進出という社会背景を映し出しています。学術的な視点から見れば、ファッションの変遷は社会の価値観の変化と密接に連動しており、ヴィンテージの一着は、私たちにその時代の物語を雄弁に語りかけてくれます。こうした文化的な深みこそ、新品の衣類では得難い、リユースならではの魅力です。
「一点物」がもたらす自己表現とファッションの多様性
大量生産・大量消費を前提とする現代のファッション市場において、多くの人々が同じようなスタイルの服を身につける傾向があります。その中で、古着は「一点物」としての希少価値を提供してくれます。
消費者行動分析の観点からも、特に若い世代を中心に、他者との差別化や個性的な自己表現を求める傾向が強まっています。誰とも被らないユニークな一着は、自分だけのスタイルを確立するための強力なツールとなります。リユースファッションの普及は、画一的になりがちなストリートの風景に彩りを与え、ファッション全体の多様性を豊かにすることに貢献していると考えられます。
寄付や支援に繋がる社会貢献としての側面
リユースという行為は、グローバルな社会貢献にも繋がっています。私たちが手放した衣類は、NPOや支援団体を通じて、国内外の衣類を必要とする人々のもとへ届けられたり、その売上が社会課題の解決のために活用されたりするケースがあります。
主な社会貢献の形
- 開発途上国支援: NPO法人「フルクル」のように、古着を換金し、その収益をミャンマーやベトナムでの学校建設や環境保全活動に充てる取り組みがあります。
- 国内の貧困支援: 日本国内の生活困窮者や児童養護施設へ衣類を届ける活動も行われています。
- ワクチン寄付: 「古着deワクチン」のように、古着の回収キットを購入することで、開発途上国の子どもたちにポリオワクチンを寄付できるプログラムも存在します。
このように、一着の服をリユースすることは、生産者から消費者、そして次の使用者や支援を必要とする人々まで、すべてのステークホルダー(利害関係者)を巻き込み、より良い社会を構築するための一助となり得るのです。
よくある質問(FAQ)
Q1: 古着とヴィンテージの違いは何ですか?
A1: 一般的に、古着は一度使用された衣類全般を指します。一方、ヴィンテージは製造から特定の年数(例えば20〜30年以上)が経過し、その時代を象徴するデザインや希少性など、歴史的・文化的な価値が認められたものを指すことが多いです。私の専門的見地から補足すると、ヴィンテージはファッション史における一種の文化的資産とも評価できます。
Q2: 古着を購入する際のデメリットや注意点はありますか?
A2: デメリットとしては、一点物であるためサイズやコンディションが限られること、稀に汚れや匂いが残っている場合があることが挙げられます。購入時には、試着をしっかり行い、生地の傷みやシミ、ボタンの欠損などがないか細部まで確認することが重要です。また、返品・交換のポリシーが店舗によって異なるため、事前に確認しておくと良いでしょう。信頼できる店舗を選ぶことも、失敗を避けるための重要なポイントです。
Q3: 古着は本当に環境に良いのでしょうか?
A3: はい、環境負荷の削減に大きく貢献すると考えられます。前述の通り、新品の衣類一着の生産には大量の水やエネルギーが消費され、CO2が排出されます。古着を利用することで、これらの製造プロセスに伴う環境負荷を大幅に削減できます。私の研究分野であるライフサイクルアセスメント(LCA)の考え方に基づくと、古着のリユースは新品生産に比べて、環境負荷を劇的に低減させる効果的な手段であると言えます。
Q4: 日本のサーキュラーファッションの取り組みは海外と比べて遅れていますか?
A4: 欧州委員会が「持続可能な循環型繊維戦略」を打ち出すなど、政策面で欧州が先行している点は否めません。しかし、日本でも大手アパレル企業による回収・リサイクルプログラムや、優れた再生技術を持つベンチャー企業の登場など、独自の取り組みが進展しています。官民が連携し、日本ならではの品質管理や技術力を活かした循環システムを構築していくことが、今後の重要な課題です。
Q5: 「安い」以外の基準で古着を選ぶには、どこを見れば良いですか?
A5: 以下の3つの視点を持つことをお勧めします。
- 品質(素材と縫製): 良質な天然素材や、丁寧な縫製が施された服は、時代を超えて長く着用できます。タグや縫い目を注意深く見てみてください。
- 物語(背景とストーリー): その服が持つデザインの時代性やブランドの歴史を知ることで、単なるモノとしてではなく、愛着の湧く一着となります。
- 自分自身の価値観: 最も大切なのは、「自分のスタイルに合うか」「長く着続けたいと心から思えるか」です。この主観的な価値観を大切にすることが、賢い選択に繋がります。
まとめ
本稿では、リユースファッションが持つ価値を「安い」という一面的な評価から解き放ち、「環境」「経済」「文化」「社会」という4つの本質的な価値を、データと専門的知見に基づいて解説しました。
一着の古着を選ぶという行為は、単なる節約に留まりません。それは、環境負荷を定量的に削減し、新たな経済圏と雇用を創出し、豊かなファッション文化を次世代に継承し、そしてグローバルな社会貢献にも繋がるという、複合的な価値を持つ選択です。
これからは価格のタグを見るだけでなく、その一着が内包するストーリーや背景にも目を向け、あなた自身の価値基準でファッションを選んでみませんか。その主体的な選択こそが、大量生産・大量消費の潮流を変え、持続可能で多様性に富んだファッションの未来を創る、確かな一歩となるはずです。