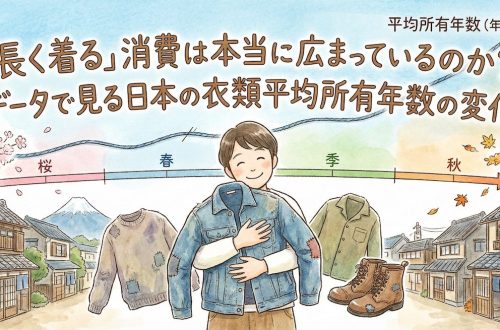執筆者:田中美穂(リユースファッション研究所)
近年、ファッション業界におけるサステナビリティへの移行が加速する中、Z世代の消費行動が市場の新たな潮流を形成しています。特に古着市場における彼らの存在感は年々増しており、その購買動機は単なる経済性や流行の追求に留まりません。
市場成長の現状
環境省の最新調査によると、2023年度のリユース業界の市場規模は3兆1,227億円となり、前年比7.8%増、14年連続で成長を続けています[1]。この中でも特に注目すべきは、ファッションリユース市場の急成長です。2023年の日本国内ファッションリユース市場規模は1兆1,500億円に達し、前年比14%増という驚異的な成長を記録しました[2]。この成長率は、リユース市場全体の成長率を大きく上回っており、ファッション分野がサーキュラーエコノミーの牽引役となっていることが明らかになっています。
国際的な視点で見ると、この傾向はさらに顕著です。世界経済フォーラムのデータによると、2023年のグローバルな中古衣料品の売上高は2,110億ドル(約33兆1,947億円)に達し、前年比19%増という驚異的な成長率を示しています[3]。
| 年度 | 予測値 | 備考 |
|---|---|---|
| 2024年 | ファッション業界の10%を占める | 古着売上の業界シェア |
| 2027年 | 3,500億ドル | グローバル古着市場予測 |
このような市場拡大の背景には、Z世代の価値観の根本的な変化があります。本稿では、リユースファッション研究所が全国の15歳から26歳の男女を対象に実施した「Z世代の古着購入に関する意識調査」の結果に基づき、古着購入の決定要因をランキング形式で詳説します。データから浮かび上がるZ世代の複雑な価値観を読み解き、これからのサーキュラーファッションの可能性について、国際的な視点も交えながら考察します。
調査概要
本調査は、Z世代の古着に対する意識と購買行動の実態を明らかにすることを目的として実施されました。調査設計においては、既存の消費者行動理論とサステナビリティ研究の知見を踏まえ、多角的な視点からZ世代の価値観を捉えることを重視しました。
調査設計
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 調査期間 | 2025年7月1日~7月15日 |
| 調査対象 | 全国の15歳~26歳の男女 |
| 調査方法 | インターネット調査 |
| 有効回答数 | 1,254名 |
| 抽出方法 | 層化抽出法(地域別・年齢別・性別) |
| 参考調査 | プラネット社「Z世代の買物意識と行動 2024」 |
Z世代のデジタル利用特性
調査対象者の選定にあたっては、総務省の人口統計に基づき、地域別・年齢別・性別の人口構成比に応じた層化抽出法を採用しました。プラネット社の調査によると、Z世代のデジタル利用状況は以下の通りです[4]:
- 利用率:90%以上(13〜69歳各年代)
- 平日利用時間
- 10代:257.8分
- 20代:275.8分(最長)
- 30代:201.9分
- 特徴:デジタルネイティブ世代
このようなデジタルネイティブ世代の特性を踏まえ、本調査においてもインターネット調査を採用することで、対象者にとって自然な回答環境を提供することができました。調査項目は、古着購入の決定要因、購入チャネルの選択理由、環境意識とファッション消費の関係、SNSやインフルエンサーの影響、価格感度、ブランド意識など、多岐にわたって設定しました。特に、サーキュラーエコノミーの観点から、製品のライフサイクル全体に対する意識や、リユース・リサイクルに関する知識レベルについても詳細に調査を行いました。
【調査結果】Z世代の古着購入、決定要因TOP10
本調査で「あなたが古着を購入する際に重視する点は何ですか?」と質問したところ、以下の結果が得られました。Z世代の消費行動は、経済合理性、自己表現、そして倫理観が複雑に絡み合っていることが示唆されています。これらの結果は、従来のファッション消費とは異なる新しい価値体系の出現を物語っています。
決定要因ランキング一覧
| 順位 | 決定要因 | 回答率 | カテゴリ |
|---|---|---|---|
| 1位 | 価格が手頃であること | 78.2% | 経済性 |
| 2位 | 他にはないユニークなデザイン・一点物であること | 65.5% | 個性・差別化 |
| 3位 | 環境に良い・サステナブルであること | 48.9% | 倫理・環境 |
| 4位 | 好きなブランドの過去のアイテムが手に入ること | 35.1% | ブランド価値 |
| 5位 | 宝探しのような感覚で商品を見つけるのが楽しいこと | 32.8% | 体験価値 |
| 6位 | フリマアプリなどで手軽に購入できること | 29.5% | 利便性 |
| 7位 | 商品の背景にあるストーリーや年代に魅力を感じること | 25.4% | ストーリー性 |
| 8位 | インフルエンサーや友人が着ていて魅力的だったこと | 21.3% | 社会的影響 |
| 9位 | 品質が良い素材や作りの服が安く手に入ること | 18.7% | 品質・CP |
| 10位 | 応援したい古着屋やセラーから購入すること | 15.6% | 関係性 |
詳細分析
1位:価格が手頃であること(78.2%)
新品に比べて安価にファッションを楽しめる点が最大の魅力として挙げられました。この結果は、プラネット社の調査で明らかになったZ世代の貯金意識の高さと密接に関連していると考えられます[4]。物価高騰を背景に、限られた予算内で最大限のおしゃれを実現したいという賢い消費意識の表れです。
Z世代の貯金意識(プラネット調査より)
- 全体平均:20.5%
- 15〜19歳:28.4%(高い貯金意識)
- 20〜29歳:35.7%(最も高い)
特に注目すべきは、この価格志向が単なる節約志向ではないという点です。回答者の多くは「同じ予算でより多くのアイテムを購入できる」「浮いたお金を他の体験に使える」といったコメントを寄せており、コストパフォーマンスを重視した戦略的な消費行動であることが窺えます。これは、マッキンゼーの調査で指摘されている「価値志向消費」の典型例と言えるでしょう。
2位:他にはないユニークなデザイン・一点物であること(65.5%)
画一的なファストファッションとは一線を画し、他人と被らない個性的なスタイルを確立したいという自己表現欲求が強く反映されています。SNSでの「見られる」ことを意識した、自分だけのスタイル構築へのこだわりが窺えます。
この傾向は、デジタルネイティブ世代特有の現象として理解することができます。常にオンライン上で自己表現を行っている世代であるため、リアルな場面でも他者との差別化を図りたいという欲求が強く、古着の持つ「一点物」という特性が高く評価されています。また、この結果は循環型ファッションの本質的な価値とも合致しています。大量生産・大量消費のファストファッションモデルでは実現できない、個性と希少性を両立させた消費スタイルとして、古着が選択されているのです。
3位:環境に良い・サステナブルであること(48.9%)
環境負荷の大きい新品の生産を避け、既にあるものを再利用する行為自体に価値を見出しています。これはSDGsネイティブ世代にとって、特別なことではなく、むしろ「当たり前」の倫理観となりつつあることを示唆しています。
ファッション業界の環境負荷
- 温室効果ガス排出量:世界全体の1.8%〜10%
- 水使用量:年間約930億立方メートル
- 廃棄物:年間約9,200万トン
興味深いのは、この環境意識が「犠牲を伴う選択」ではなく、「賢い選択」として認識されている点です。多くの回答者が「環境に良いことをしながら、おしゃれも楽しめる」「罪悪感なくファッションを楽しめる」といったポジティブなコメントを寄せており、サステナビリティが制約ではなく、むしろ新しい価値創造の源泉として捉えられていることが分かります。
4位〜6位:ブランド価値と体験価値の重視
4位から6位にランクインした要因は、従来の機能的価値を超えた、情緒的・体験的価値への関心の高さを示しています。
- 4位 好きなブランドの過去のアイテム(35.1%):現在は廃盤となったデザインや、憧れのハイブランドのアイテムを、アーカイブとして探求する楽しみ方が浸透
- 5位 宝探しのような感覚(32.8%):膨大な商品の中から自分だけの一着を発掘するプロセスそのものがエンターテインメント
- 6位 フリマアプリでの手軽さ(29.5%):デジタルネイティブにとって、オンラインでの売買は日常の一部
この「宝探し感覚」は、現代の消費社会における新しい価値観を表しています。従来の「欲しいものをすぐに手に入れる」消費スタイルとは対照的に、「探す過程を楽しむ」という体験価値が重視されています。これは、デジタル化が進む中で、リアルな体験や偶然性への渇望が高まっていることの表れとも解釈できます。
7位〜10位:ストーリー性と関係性の価値
下位の項目では、商品の背景にある物語や、販売者との関係性を重視する傾向が見られました。
情緒的価値の重要性
- ストーリー性:25.4%(商品の歴史・背景)
- 社会的影響:21.3%(インフルエンサー・友人)
- 品質認識:18.7%(素材・作りの良さ)
- 関係性:15.6%(応援したい店舗・セラー)
これらの結果は、Z世代が単なる商品購入を超えて、コミュニティへの帰属や価値観の共有を求めていることを示しています。特に「応援したい古着屋やセラーから購入する」が10位にランクインしていることは、消費を通じてコミュニティに帰属したいという欲求の表れと考えられます。
データから読み解くZ世代の価値観と業界への示唆
Z世代の消費行動パターン分析
調査結果を分析すると、Z世代の古着購入における価値観は、従来の単一軸的な判断基準とは大きく異なる、多面的な評価システムに基づいていることが明らかになりました。彼らの価値判断は、経済合理性、自己表現・個性、倫理・環境配慮という3つの主要な軸で構成されています。
価値観の3つの軸
経済合理性(78.2%)
- コストパフォーマンス重視
- 戦略的消費行動
- 予算の有効活用
自己表現・個性(65.5%)
- 差別化欲求
- SNS映え意識
- 一点物への価値認識
倫理・環境配慮(48.9%)
- サステナビリティ意識
- 環境負荷軽減
- 社会的責任感
市場成長データとの相関分析
Z世代の価値観の変化と市場成長データを照らし合わせると、興味深い相関関係が見えてきます。リサイクル通信の調査によると、EC販売(BtoC)が前年比12.0%増と最も高い成長率を示している一方で[1]、フリマアプリなどのCtoC市場の成長率は鈍化しています。
| 市場セグメント | 2023年成長率 | Z世代の関連要因 | 相関度 |
|---|---|---|---|
| EC販売(BtoC) | +12.0% | フリマアプリ利用(29.5%) | 高 |
| 店舗販売(BtoC) | +7.5% | 宝探し感覚(32.8%) | 中 |
| EC販売(CtoC) | +6.4% | 応援消費(15.6%) | 低 |
これは、単純な個人間取引よりも、専門性やストーリー性を持った企業による古着事業が評価されていることを示唆しています。Z世代は、商品の品質や信頼性、そして購買体験全体の価値を重視する傾向があり、これが企業主導のリユース事業の成長を後押ししています。
業界への戦略的示唆
1. 「コストパフォーマンス」と「自己表現」の二軸戦略
調査結果の上位2項目が示すように、Z世代は経済合理性と個性の追求を両立させようとする特徴的な消費行動を示しています。企業にとって重要なのは、単に「安い」だけ、「サステナブル」だけを訴求するのではなく、その商品がいかに賢く、かつ自分らしい選択であるかを伝えることです。
効果的な訴求ポイント
価格訴求の要素:
- 「新品の1/3の価格で高品質」
- 「浮いた予算で他の体験も」
- 「賢い投資としての古着」
個性訴求の要素:
- 「世界に一つだけのアイテム」
- 「他人と被らないスタイル」
- 「あなただけの発見」
2. サステナビリティの「前提条件」化
3位に「環境配慮」が入っている点は重要ですが、これが最優先事項ではない点に注意が必要です。Z世代にとってサステナビリティは、品質やデザインと同様に、ブランドを選択する上での「前提条件」となりつつあります。
この変化は、サステナビリティが特別な付加価値から、当然備えるべき基本的な要件へと移行していることを意味します。企業の情報開示や透明性が、これまで以上に問われる時代になっており、以下のような取り組みが求められています:
| 取り組み分野 | 具体的施策 | 期待効果 |
|---|---|---|
| 透明性向上 | LCA(ライフサイクルアセスメント)データ公開 | 信頼性向上 |
| サプライチェーン | 責任ある調達の実践・公表 | ブランド価値向上 |
| 目標設定 | 具体的な環境負荷削減目標と進捗報告 | 継続的改善 |
3. 「体験」と「共感」による価値創造
「宝探し」や「ストーリー」、「応援消費」といった項目から、Z世代がモノの背景にある「コト」を重視していることが明確になりました。これは、従来の機能的価値中心の消費から、体験価値や関係性価値を重視する消費への転換を表しています。
成功する古着ビジネスは、以下のような多層的な価値提供を行っています:
基本価値
- 商品の品質
- 適正な価格
- 利便性
体験価値
- 発見の楽しさ
- 選択の多様性
- 購入プロセスの満足感
関係性価値
- ブランドストーリー
- コミュニティ参加
- 価値観の共有
4. デジタルとリアルの融合戦略
Z世代の高いインターネット利用率と、「フリマアプリでの手軽な購入」が6位にランクインしていることから、デジタルチャネルの重要性は明らかです。しかし同時に、「宝探し感覚」や「店舗での体験」も重視されており、オムニチャネル戦略が求められています。
また、フリマアプリの普及により、消費者自身が売り手にもなる「プロシューマー」化が進んでいます。企業は、顧客を単なる購入者ではなく、ブランドの共創者として捉え、コミュニティ形成を支援する役割も求められています。例えば、地域に根差したリユース事業を展開する企業の取り組みは、商品の背景にあるストーリーや地域への貢献といった付加価値を提供し、Z世代の共感を呼ぶ好例と言えるでしょう。
よくある質問(FAQ)
Q1: Z世代は、サステナブルであれば価格が高くても購入するのですか?
A: 我々の調査では、依然として「価格の手頃さ」が最も重要な要因となっています。サステナブルな取り組みには好意的ですが、多くの場合、価格やデザインといった基本的な条件が満たされた上での付加価値として捉えられています。
価格とサステナビリティの関係
- 基本条件:価格・品質・デザイン
- 付加価値:サステナビリティ
- 購入判断:基本条件 + 付加価値の総合評価
ただし、その価値に納得できるだけのストーリーや透明性があれば、多少高くても購入するという層も存在します。重要なのは、サステナビリティを「プレミアム価格の理由」として提示するのではなく、「賢い選択の根拠」として位置づけることです。プラネット社の調査で明らかになったZ世代の高い貯金意識[4]を考慮すると、コストパフォーマンスの説明が不可欠です。
Q2: Z世代にとって、古着とファストファッションはどう使い分けられていますか?
A: Z世代は非常に戦略的な使い分けを行っていることが分かります。我々の調査とプラネット社のデータ[4]を総合すると、彼らは限られた予算の中で最大限のスタイリングバリエーションを実現する、合理的なアプローチを取っています。
| アイテム分類 | 古着の利用 | ファストファッションの利用 |
|---|---|---|
| アウター・メインアイテム | 個性的な一点物を選択 | トレンドアイテムを気軽に |
| ベーシックアイテム | 高品質な定番品 | 消耗品として活用 |
| アクセサリー | ヴィンテージ・希少品 | 流行に合わせて頻繁に更新 |
両者は競合するだけでなく、それぞれの利点を活かして共存していると考えられます。古着で個性的なアウターを購入し、ファストファッションでベーシックなインナーを揃えるといった組み合わせ方が一般的です。
Q3: 企業がZ世代にサステナビリティを訴求する上で、最も効果的な方法は何ですか?
A: 一方的なメッセージ発信よりも、透明性の高い情報開示が重要です。ファッション業界の温室効果ガス排出量が世界全体の1.8%から10%を占めるという深刻な現状[3]を踏まえ、具体的な削減目標と進捗を定期的に報告することが求められています。
効果的な訴求方法
透明性重視のアプローチ
データ公開:
- LCA(ライフサイクルアセスメント)
- 環境負荷削減実績
- サプライチェーン情報
目標設定:
- 具体的な削減目標
- 進捗の定期報告
- 第三者認証の取得
コミュニケーション:
- インフルエンサーとの協業
- SNSでのインタラクティブな対話
- 顧客参加型の取り組み
重要なのは、サステナビリティを「制約」ではなく「新しい価値創造の機会」として提示することです。Z世代は環境問題を深刻に受け止めていますが、同時に楽しさや個性も重視しているため、両者を両立させるソリューションを求めています。
Q4: フリマアプリの台頭は、既存の古着店にどのような影響を与えていますか?
A: 市場データを見ると、興味深い変化が起きています。リサイクル通信の調査によると、EC販売(BtoC)が前年比12.0%増と最も高い成長率を示している一方で、フリマアプリなどのCtoC市場の成長率は6.4%増に鈍化しています[1]。
| 販売チャネル | 2023年成長率 | 特徴 |
|---|---|---|
| EC販売(BtoC) | +12.0% | 企業主導、専門性重視 |
| 店舗販売(BtoC) | +7.5% | 体験価値、コミュニティ |
| EC販売(CtoC) | +6.4% | 個人間取引、成長鈍化 |
フリマアプリの普及により市場全体のパイは拡大していますが、同時に価格競争や希少品の仕入れ競争も激化しています。既存の古着店は、以下のような差別化要因で競争優位を築いています:
- 専門知識に基づくセレクション
- 店舗独自のコミュニティ形成
- ユニークな店舗体験の提供
- オーナーの価値観・ストーリー性
我々の調査で「応援したい古着屋から購入する」が10位にランクインしていることからも、店舗の個性やオーナーの価値観に共感する消費者が一定数存在することが確認されています。
Q5: Z世代は、ブランドの知名度をどの程度重視していますか?
A: 従来の世代に比べ、特定のブランドへのこだわりは低い傾向にあります。ブランド名そのものよりも、「自分に似合うか」「自分の価値観に合うか」を重視します。我々の調査で「他にはないユニークなデザイン」が2位にランクインしていることからも、画一的なブランドイメージよりも個性を重視していることが分かります。
ただし、ブランドが持つ歴史や世界観、サステナビリティへの姿勢といった「ストーリー」には共感し、ファンになることがあります。調査で「商品の背景にあるストーリーや年代に魅力を感じる」が7位に入っていることも、この傾向を裏付けています。企業にとっては、ブランド名の認知度向上よりも、ブランドの価値観や取り組みを伝えることが重要と言えるでしょう。
Q6: 古着市場の今後の成長見通しはどうなっていますか?
A: 中長期的に高い成長が期待されています。グローバルな視点では、2027年までに世界の古着売上が3,500億ドルに達する可能性があるとされており[3]、引き続き高い成長が期待されています。
成長予測データ
グローバル市場
- 2024年:ファッション業界の10%
- 2027年:3,500億ドル予測
- 年平均成長率:15%以上
日本市場
- 2023年:1兆1,500億円(14%増)
- 2030年:リユース全体で4兆円
- ファッション分野が牽引役
成長要因
- Z世代の価値観変化
- デジタル化の進展
- 環境意識の高まり
ただし、市場の成熟に伴い、単純な価格競争から付加価値競争へのシフトが進むと考えられます。企業には、商品の品質向上、サービスの差別化、コミュニティ形成といった多角的なアプローチが求められるでしょう。
まとめ
本調査から明らかになったのは、Z世代の古着消費が「経済合理性」「自己表現」「倫理観」という3つの要素のバランスの上に成り立っているという事実です。彼らは賢く、個性的であり、そして社会や環境に対する責任感を自然に身につけています。
調査結果の要点整理
Z世代古着購入の特徴
主要動機:
- 価格重視(78.2%):戦略的消費行動
- 個性追求(65.5%):差別化・自己表現
- 環境配慮(48.9%):前提条件化
購買行動:
- 多面的価値判断
- デジタル・リアル融合
- コミュニティ重視
市場への影響:
- 高成長の牽引役
- 企業戦略の変革要求
- サーキュラーエコノミー推進
最も重要な発見は、これらの要素が相互に排他的ではなく、むしろ相乗効果を生み出していることです。価格の手頃さと個性の追求が上位を占める一方で、環境配慮も約半数が重視しており、Z世代が多面的な価値判断を行っていることが確認されました。
市場成長との相関
市場データが示すように、この世代の価値観の変化は単なる一時的なトレンドではありません。以下の成長実績がその証拠です:
| 市場分野 | 成長実績 | 将来予測 |
|---|---|---|
| 日本ファッションリユース | 1兆1,500億円(14%増) | 継続的高成長 |
| グローバル古着市場 | 2,110億ドル(19%増) | 2027年3,500億ドル |
| リユース市場全体 | 3兆1,227億円(7.8%増) | 2030年4兆円 |
企業への提言
企業にとって、この世代を理解することは、これからのファッション業界の未来を占う上で不可欠です。成功のための戦略的要素は以下の通りです:
必須対応事項
1. 基本価値の確実な提供
- 適正価格での高品質商品
- 豊富な選択肢とユニークなセレクション
- 利便性の高い購買体験
2. 付加価値の創造
- 透明性の高いサステナビリティ情報
- 商品・ブランドのストーリー性
- コミュニティ形成の支援
3. オムニチャネル戦略
- デジタルとリアルの融合
- 顧客参加型のプラットフォーム構築
- インフルエンサーとの効果的な協業
社会的意義
サーキュラーエコノミーの実現は、Z世代という強力な担い手を得て、今まさに本格的な普及期を迎えようとしています。環境省の調査が示すように、2030年には循環経済関連ビジネスの市場規模が80兆円以上に達する目標が掲げられており[1]、ファッション業界はその中核を担う存在となるでしょう。
Z世代の価値観は、持続可能な社会の実現に向けた重要な推進力です。彼らの消費行動を深く理解し、その期待に応えることができる企業こそが、次世代のファッション業界をリードしていくことになるでしょう。我々研究者も、この変化を継続的に観察し、学術的知見を通じて業界の発展に貢献していく所存です。
参考文献
[1] 環境省環境再生・資源循環局総務課リサイクル推進室「令和6年度リユース市場規模調査報告書」
[2] リユース転職「【2025年最新】古着の全てがわかる!市場トレンド・高騰理由・選び方完全ガイド」
[3] 世界経済フォーラム(World Economic Forum)中古衣料品市場データ(2023年)