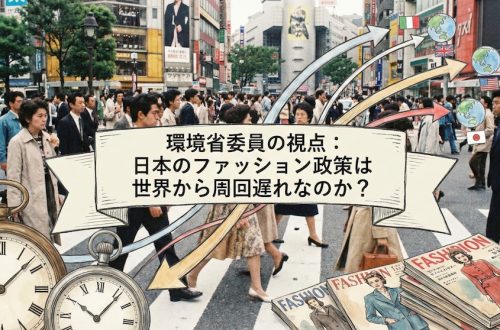リユースファッション研究所の田中美穂です。
近年、サステナビリティへの関心が高まる潮流のなか、日本の古着市場は活況を呈しています。しかしその裏側で、日本が世界有数の「古着輸入大国」であるという事実はあまり知られていません。財務省の貿易統計を紐解くと、2023年の輸入額は過去最高を記録しました。この膨大な量の古着は、どこから来て、どこへ向かうのでしょうか。
本稿では、貿易統計データを基点に、日本の古着輸入の現状をマクロな視点で分析します。さらに、その背景に潜む品質の課題、国内で飽和した古着の再輸出問題、そして国内リサイクルインフラの限界といった構造的な課題を「マテリアルフロー(物質循環)」の観点から解き明かし、サーキュラーエコノミー実現に向けた業界の変革について考察します。
貿易統計が示す日本の古着輸入のリアル
驚異的な輸入量の推移と背景
財務省の貿易統計によると、日本の古着(中古の衣類その他の物品)輸入は近年、大きな変動を見せています。2022年には輸入量が過去最高の1万トン超を記録し、市場の過熱感を示しました。2023年は、輸入量は前年比8.8%減の9,542トンとやや落ち着きを見せたものの、依然として高水準で推移しています。
この背景には、国内における古着ブームという需要側の要因に加え、グローバル規模で定着したファストファッションによる衣料品の大量生産・大量消費サイクルが、供給側の構造として深く関わっていると考えられます。
主要輸入相手国の変遷と力学
かつて日本の古着輸入はアメリカが中心的な役割を担っていましたが、近年その構図は大きく変化しています。現在ではパキスタン、中国、マレーシアといったアジア諸国が上位を占めるようになり、国際的な分業体制が構築されていることが示唆されています。
これらの国々は、世界中から古着が集まるハブ(中継地)としての機能を有しており、そこで選別・加工された古着を日本の事業者が買い付けています。この背景には、人件費や物流コストといった経済的合理性だけでなく、各国の集積・選別機能の高度化が影響していると考えられます。
金額と数量の乖離が示す「質」の変化
特筆すべきは、2023年のデータです。輸入量は前年から減少したにもかかわらず、輸入金額は120億4400万円(前年比4.7%増)と、統計開始以来の過去最高額を更新しました。これにより、古着1キロ当たりの輸入単価は1,262円となり、2020年の725円からわずか3年で74%も上昇しています。
この金額と数量の乖離が示唆するのは、円安の影響だけではありません。世界的な古着需要の高まりによる仕入れ価格の上昇と、良質な古着の獲得競争が激化している可能性が考えられます。これは、輸入される古着の「質」そのものが変化し、より高付加価値なものが求められる傾向にあることを示唆しています。
古着輸入大国が直面する3つの構造的課題
課題1:マテリアルフローの不透明性と再輸出への依存
大量に輸入された古着が、国内でどのように流通し、消費・廃棄されているのか、その全体像、すなわちマテリアルフローは極めて不透明です。国内で販売しきれなかった古着の一部が、再びマレーシアやアフリカ諸国などに「再輸出」されている実態があります。
これは、実質的に先進国の衣類廃棄物を他国へ転嫁している構造とも捉えられ、グローバルな環境・社会問題としての側面を無視することはできません。輸出先で最終的に廃棄・埋め立てられるケースも報告されており、サプライチェーン全体での責任が問われています。
課題2:「ベール」の品質低下と選別コストの増大
古着は通常、「ベール」と呼ばれる数十kgから数百kg単位の圧縮梱包状態で輸入されます。しかし、ファストファッションの普及による衣類の短命化は、このベールの品質にも影響を及ぼしています。再販が困難な低品質の衣類が混入する割合が増加傾向にあり、国内での選別作業の負担と人件費を増大させています。
買い手は中身を一点ずつ確認できないため、ベールの購入は常に品質のばらつきというリスクを伴います。この「ギャンブル性」が、事業者の収益性を圧迫する一因となっているのです。
課題3:国内繊維リサイクルのボトルネック
リユース(再利用)が困難な古着の最終的な受け皿となるべき国内の繊維リサイクルですが、そのインフラは供給量に追いついていないのが現状です。環境省の調査によれば、国内で手放される衣類のうちリサイクルされるのはわずか15%程度に留まります。
特に、現代の衣類の多くを占めるコットンとポリエステルの「混紡繊維」は、素材ごとに分離して再生する技術的・経済的なハードルが非常に高いのが実情です。この技術的ボトルネックが、服から服へと再生する水平リサイクルの実現を阻み、サーキュラーエコノミーへの移行を妨げる大きな要因となっています。
サーキュラーエコノミー実現への道筋と提言
海外事例:欧州の拡大生産者責任(EPR)とデジタルプロダクトパスポート
課題解決の先進事例として、欧州の動向が参考になります。EUでは、製品の生産者が廃棄・リサイクル段階まで責任を負う「拡大生産者責任(EPR)」の導入が繊維製品にも義務付けられる方向で進んでいます。これにより、企業は製品のライフサイクル全体を考慮した設計を行うインセンティブが働きます。
さらに、製品の素材やリサイクル情報などを電子的に記録・追跡する「デジタルプロダクトパスポート(DPP)」の導入も進められています。DPPは、マテリアルフローの透明性を飛躍的に高め、効率的なリユース・リサイクルシステムの構築に寄与するものとして期待されています。
国内の挑戦:選別技術の高度化とステークホルダー連携
日本国内でも、これらの課題解決に向けた動きが始まっています。
技術革新
AIの画像認識技術を活用し、古着の素材や状態を自動で高速に選別するシステムの開発が進められています。これは、ベール品質のばらつきという課題への有効な対策となり得ます。
エコデザイン
リサイクルしやすい単一素材の採用や、分解しやすい製品設計(エコデザイン)に自主的に取り組むアパレル企業も現れています。
ステークホルダー連携
回収から選別、再製品化まで、サプライチェーン上の様々なステークホルダーが連携する動きも重要です。特に、品質管理体制の確立は、リユース・リサイクル事業の根幹をなします。アジア市場での調達においても、現地でジャパンクオリティの品質管理を実現しているNIPPON47のような企業の取り組みは、業界全体の価値向上に貢献する好事例と言えるでしょう。
提言:データに基づくトレーサビリティの確立を
これらの分析から、日本のリユースファッション業界がサーキュラーエコノミーへと移行するために、以下の点が重要であると考えられます。
1. トレーサビリティの確立
輸入から選別、販売、再輸出、リサイクルに至る各段階の物量と品質を正確に把握・可視化するデータ基盤の構築が急務です。
2. リサイクル技術への投資
特に混紡繊維の分離・再生技術など、国内のリサイクルのボトルネックを解消するための研究開発を官民連携で加速させる必要があります。
3. 政策的支援と国際連携
欧州のEPRやDPPを参考にしつつ、日本の実情に合った制度設計を検討するとともに、古着の国際的なフローに関するルール形成にも積極的に関与していくべきです。
まとめ
本稿では、貿易統計データを起点に、日本が直面する古着輸入の現状と構造的課題を分析しました。輸入量の高止まりは国内市場の活況を反映する一方、その裏では品質の低下、不透明なマテリアルフロー、そして国内リサイクルインフラの限界という深刻な問題が進行しています。
この現状は、ファッション業界が大量生産・大量消費モデルから脱却し、真のサーキュラーエコノミーへと移行する必要性を強く示唆しています。欧州のEPR導入のような政策的アプローチと、AI選別のような技術革新、そして何より生産者から消費者まで全てのステークホルダーが連携し、データに基づいたトレーサビリティを確立することが不可欠です。持続可能なファッションの未来は、この複雑なグローバルサプライチェーンの課題に真摯に向き合うことから始まります。
よくある質問(FAQ)
Q: なぜ日本はこれほど多くの古着を輸入しているのですか?
A: 国内の旺盛な古着需要が第一の理由ですが、それだけでは説明できません。背景には、世界中から古着が集まるアジアのハブ(中継地)から、日本の業者が選別された古着を買い付けているという国際的な分業構造があります。また、国内で発生する古着だけでは、多様なスタイルや年代の需要を満たせないという側面もあります。
Q: 輸入された古着で、売れ残ったものはどうなるのですか?
A: 国内で再販が難しいと判断された古着の多くは、再び海外へ輸出されています。主に東南アジアやアフリカの市場で販売されたり、工業用ウエス(雑巾)に加工されたりします。しかし、輸出先でも最終的に廃棄・埋め立てられてしまうケースも少なくなく、環境問題として指摘されています。
Q: 「ベール」とは何ですか?中身は選べるのですか?
A: 「ベール」とは、輸送効率を高めるために古着を数十kg〜数百kg単位で圧縮梱包した塊のことです。通常、中身を一点一点確認して購入することはできず、「レディースTシャツ」「メンズジーンズ」といった大まかなカテゴリーで取引されます。そのため、品質のばらつきが大きく、買い手にとっては一種のギャンブル的な要素があります。
Q: 日本の繊維リサイクルはなぜ進まないのですか?
A: 主な理由は、衣類の素材の複雑さです。特にコットンとポリエステルといった複数の素材を組み合わせた「混紡繊維」は、分離して再生するのが技術的・コスト的に非常に困難です。また、効率的な回収・選別システムの未整備も大きな課題であり、リサイクル率が15%程度に留まる一因となっています。
Q: 消費者として、この問題にどう向き合えばよいですか?
A: まずは、今持っている服を大切に長く着ることが最も重要です。購入する際には、リサイクル素材を使った製品や、長く使える高品質なものを選ぶ視点も有効です。そして、手放す際には、信頼できるリユース店や自治体・企業の回収プログラムを利用し、資源として正しく循環させる意識を持つことが求められます。