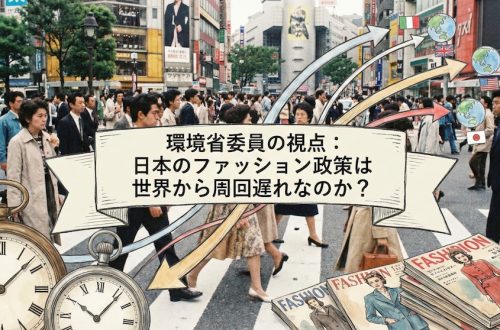執筆者:田中 美穂(株式会社サステナブル・ファッション・ラボ 代表取締役 / 早稲田大学商学学術院 客員研究員)
近年、ファッション業界においてリユース市場、特にオンラインでの古着取引が急速な拡大を見せています。環境省の調査によると、2024年のリユース市場規模は約3兆5千億円に達し、成長を続けています。 この成長の背景には、単なる節約志向だけでなく、Z世代を中心に高まるサステナビリティへの意識があります。
しかし、数ある古着ECプラットフォームの中で、私たちはどのサービスを選ぶべきなのでしょうか。本稿では、サステナブルファッション研究者の視点から、国内主要3大プラットフォーム「メルカリ」「ZOZOTOWN(ZOZOUSED)」「ラクマ」を、従来の利便性比較に留まらず、「持続可能性」と「将来性」という新たな評価軸で徹底的に分析・比較します。データと国際的な動向を踏まえ、読者の皆様が自身の価値観に合った、真に未来志向の選択をするための一助となれば幸いです。
【この記事の結論】3大古着EC、結局どれを選ぶべき?
| 項目 | メルカリ | ZOZOTOWN (ZOZOUSED) | ラクマ |
|---|---|---|---|
| ビジネスモデル | CtoC (個人間取引) | BtoC (企業が買取・販売) | CtoC (個人間取引) |
| サステナビリティ | CO2削減量を可視化し、社会全体の循環を目指す | 「買い替え割」で効率的な衣料品循環ループを構築 | 楽天経済圏との連携でユーザー参加を促進 |
| 強み・特徴 | 商品の多様性と手軽さが魅力。ユーザー主導のコミュニティ | 品質の信頼性が高く安心。プロが検品・管理 | 楽天ポイントが使えてお得。手数料が比較的安い |
| 将来性のカギ | AI鑑定などテクノロジー活用による信頼性向上 | 一次流通(新品)との連携とトレーサビリティ確保 | 楽天のビッグデータ活用による循環促進策 |
目次
なぜ今、古着ECの「持続可能性」が重要なのか?市場動向と消費者意識の変化
リユース市場の現状:拡大する市場規模と二次流通の役割
リユース市場は成長の一途をたどっており、2022年には約2.9兆円規模に達し、13年連続で拡大しています。 特にフリマアプリとネットオークションを合わせたCtoC(個人間取引)市場は、物価高や環境意識の高まりを背景に市場全体の拡大を牽引しています。
ファッション業界において、この二次流通市場が果たす役割は極めて重要です。新品の衣料品一着が生産から廃棄されるまでに排出するCO2は平均約25.5kgと言われており、二次流通の活性化は、新品の生産量を抑制し、製品ライフサイクル全体での環境負荷を低減させるサーキュラーエコノミー(循環型経済)の根幹をなすものと考えられます。
消費者意識の変化:Z世代が牽引する「倫理的消費」
市場拡大の背景には、消費者、特にZ世代の意識変化が大きく影響しています。メルカリ総合研究所の2024年の調査では、Z世代の71.1%が直近1年間に中古品の購入経験があり、不要品の処分方法としてもフリマアプリでの販売を積極的に活用していることが示されています。
彼らの消費行動は、単に安価であることだけを求めるものではありません。SHIBUYA109 lab.の調査によれば、Z世代がサステナブルな商品を購入する理由として「地球や社会に良いことをしたいから」が上位に挙げられており、倫理的な価値観が購買決定の重要な要因となっていることが示唆されています。 この動きは一時的なトレンドではなく、企業のESG(環境・社会・ガバナンス)への姿勢が問われる構造的な変化であると分析できます。
企業に求められる責任:ファッション業界の環境負荷と規制動向
ファッション業界は、その製造過程で大量の水資源を消費し、世界の温室効果ガス排出量の約8%を占めるとも指摘されるなど、環境負荷の大きい産業です。 Tシャツ1枚を製造するのに約2,700リットルの水が必要との試算もあり、これは人が2年半で飲む量に相当します。
こうした状況を受け、国際社会では規制強化の動きが加速しています。特に欧州では、製品の素材やサプライチェーン、リサイクル情報などを電子的に記録・追跡可能にする「デジタル製品パスポート(DPP)」の導入が2027年までに義務付けられる見込みです。 このような国際動向は、日本のプラットフォーム事業者にとっても対岸の火事ではなく、ビジネスモデルの根幹からサステナビリティへの対応を迫られることを意味しています。
【基本比較】メルカリ・ZOZOTOWN・ラクマのビジネスモデルと特徴
CtoCとBtoC:ビジネスモデルの根本的な違い
3大プラットフォームを比較する上で、まず理解すべきはビジネスモデルの違いです。
- CtoC(Consumer-to-Consumer): メルカリとラクマが採用する個人間取引モデルです。プラットフォームは取引の「場」を提供し、出品から価格設定、発送までを個人が行います。
- BtoC(Business-to-Consumer): ZOZOTOWNの古着事業「ZOZOUSED」が採用するモデルです。ZOZOが個人から商品を買い取り、検品・クリーニング・撮影・保管を行った上で、自社サイトで販売します。
このビジネスモデルの違いは、手数料や利便性だけでなく、後述する環境負荷や循環の質にも大きく影響を及ぼします。
機能・手数料・ユーザー層の比較一覧表
| 項目 | メルカリ | ZOZOTOWN (ZOZOUSED) | ラクマ |
|---|---|---|---|
| ビジネスモデル | CtoC | BtoC(買取・販売) | CtoC |
| 販売手数料 | 販売価格の10% | – (買取価格に反映) | 販売価格の6.0%(税抜) |
| ユーザー数 | 月間利用者数2,300万人以上 | – | – |
| ユーザー層 | 10代〜シニアまで幅広い | 10代〜30代が中心 | 20代〜40代が中心 |
| 主な取扱ジャンル | オールジャンル | ファッション中心 | ファッション、エンタメ中心 |
| 配送方法 | らくらくメルカリ便、ゆうゆうメルカリ便(匿名配送可) | ZOZOTOWNの物流網 | かんたんラクマパック(匿名配送可) |
| 特徴的な機能 | メルカード、メルペイスマート払い、メルカリ教室 | 買い替え割、ブランド古着の品質担保 | 楽天ポイント連携、購入申請機能 |
※各データは2025年10月時点の公表情報を基に作成。
各プラットフォームの強みと弱み
- メルカリ・ラクマ(CtoC):
- 強み: 出品の手軽さ、価格交渉の自由度、商品の多様性が魅力です。ニッチなアイテムが見つかりやすく、ユーザー主導のコミュニティが形成されています。
- 弱み: 商品の品質は出品者の自己申告に依存するため、購入者側には真贋や状態を見極めるリテラシーが求められます。個人間のトラブルリスクも内在します。
- ZOZOTOWN(BtoC):
- 強み: プロによる査定、クリーニング、採寸、撮影が行われるため、品質の信頼性が高く、安心して購入できます。新品購入時に下取りを依頼できる「買い替え割」は利便性が高いです。
- 弱み: 企業が介在するため、個人が売却する際の買取価格はCtoCに比べて低くなる傾向があります。また、取り扱いブランドや商品の状態には一定の基準が設けられています。
評価軸1:サーキュラーエコノミーへの貢献度で見る各社の取り組み
メルカリ:「あらゆる価値を循環させる」エコシステムの構築
メルカリは「プラネット・ポジティブ」という概念を掲げ、事業を通じて環境課題の解決を目指す姿勢を明確にしています。 特筆すべきは、そのインパクトを定量的に評価・開示している点です。東京大学との共同研究によると、日米のメルカリでの取引を通じて年間約69万トンの温室効果ガス排出が回避されたと試算されています。 これは、衣類1点の取引あたり約9.4kgのCO2削減に相当します。
さらに、梱包材の再利用促進や、リユースに関する知識を学べる「メルカリ教室」の開催など、単なる取引の場に留まらず、循環型社会を支えるためのインフラやユーザーリテラシーの向上といったエコシステム全体の構築を目指している点が評価されます。
ZOZOTOWN:「買い替え割」が創出する衣料品循環ループ
ZOZOTOWNの「買い替え割」は、新品購入のインセンティブと不要な衣類の回収をシームレスに結びつけた、ユニークな衣料品循環の仕組みです。 ユーザーは新しい商品を購入する際に、過去にZOZOTOWNで購入した商品を下取りに出すことで、その場で割引を受けられます。
このモデルの優れた点は、消費者が最も衣類を手放す動機付けが高い「新しい服を買う」タイミングを捉え、効率的に二次流通市場へ衣類を還流させている点です。回収された衣類は専門の拠点で一括管理され、ZOZOUSEDで再販されるというマテリアルフロー(物質の流れ)が明確に設計されており、ビジネスと一体化した循環システムを構築しています。
ラクマ:楽天経済圏との連携による循環促進
ラクマの最大の強みは、楽天グループが持つ広範な経済圏との連携にあります。楽天ポイントが貯まる・使える点は、多くのユーザーにとってリユースに参加する強力なインセンティブとなります。
サステナビリティに関する独自のプログラムはメルカリやZOZOに比べて目立つものが少ないものの、楽天グループ全体としてはESGへの取り組みを進めており、その一環としての役割が期待されます。 今後は、楽天の持つビッグデータを活用し、ユーザーの購買行動に基づいたサステナブルな消費の提案など、経済圏全体での循環促進策が求められるでしょう。
評価軸2:ライフサイクルアセスメント(LCA)視点での環境負荷比較
「輸送」の環境負荷:CtoC個人間配送 vs BtoC集約型物流
私の専門であるライフサイクルアセスメント(LCA)の視点から、物流プロセスを分析すると、両モデルの特性が見えてきます。
- CtoCモデル(メルカリ・ラクマ): 全国の個人から個人へ、個別の荷物が多頻度で配送されます。これは消費者に近い場所でモノが循環するという利点がある一方、輸送ルートが分散し、積載効率が最適化されにくいという課題も考えられます。
- BtoCモデル(ZOZOTOWN): 個人からの買取品は一度ZOZOの物流拠点に集約され、そこから購入者へ発送されます。この集約型物流は、輸送ルートや配送計画を最適化しやすく、一点あたりの輸送に伴うCO2排出量を抑制できる可能性があります。
ただし、CtoCでも「まとめ買い」機能の活用や梱包材の工夫など、ユーザーの行動次第で環境負荷を低減することは可能です。
「品質管理・再販プロセス」の負荷:クリーニング・鑑定・保管
ZOZOUSEDでは、商品の価値を最大化するために、クリーニング、補修、撮影、倉庫での一元保管といったプロセスが発生します。これらは水やエネルギーを消費するため、環境負荷の一因となります。しかし、同時にこれらのプロセスは商品の寿命を延ばし、購入後の早期廃棄を防ぐという重要な役割も担っています。
ジャパンクオリティを担保する高度な検品・管理体制は、リユース品の価値を最大化する上で不可欠です。特に、今後アジア市場などへの展開を考える際、このような品質管理と効率的な物流網を現地で構築できるかが鍵となります。これを実現している企業の取り組みは、業界全体の品質向上に寄与していると考えられます。
「売れ残り・廃棄」のリスク:在庫管理と廃棄物削減への取り組み
BtoCモデルであるZOZOUSEDは、買い取った商品が売れ残った場合に在庫リスクを負います。AIを活用した需要予測や価格の最適化により廃棄ロスの削減に努めていると考えられますが、最終的に売れ残った商品の行方については、さらなる情報開示が期待されます。
一方、CtoCモデルでは在庫リスクは個々の出品者が負います。プラットフォーム側には直接的な在庫リスクはありませんが、「売れ残った衣類」が個人のクローゼットに滞留、あるいは最終的に廃棄される可能性は残ります。プラットフォームとして、売れ残り品の再資源化ルートの提供など、循環ループを閉じるための関与が今後の課題となるでしょう。
【専門家の将来予測】2025年以降、古着ECプラットフォームの勝者を分ける鍵
鍵1:テクノロジー活用(AI鑑定・パーソナライズ)
今後の競争優位性を左右する第一の鍵は、AIをはじめとするテクノロジーの活用です。AIによる真贋鑑定や状態査定の精度向上は、CtoCプラットフォームにおける信頼性の課題を解決する可能性があります。また、膨大な取引データから個々のユーザーの嗜好を分析し、最適なリユース品を提案するパーソナライゼーション技術は、顧客体験を飛躍的に向上させるでしょう。
鍵2:一次流通との連携とトレーサビリティ
二次流通市場が成熟するにつれ、新品を販売するブランド(一次流通)との連携が不可欠になります。例えば、新品購入時に将来の買取価格を保証するサービスや、製品の素材・生産履歴を追跡できるトレーサビリティ技術(ブロックチェーンなど)の導入です。これにより、消費者は安心して商品を購入・売却でき、企業は製品のライフサイクル全体を管理しやすくなります。
鍵3:国際動向と法規制への対応力
前述した欧州の「デジタル製品パスポート」のような規制は、いずれ日本市場にも影響を及ぼすと考えられます。 製品の環境負荷に関する情報開示義務や、修理可能性の担保(修理する権利)など、将来的な規制強化に柔軟に対応できるビジネスモデルとデータ基盤を持つプラットフォームが、長期的に優位に立つと予測されます。
よくある質問(FAQ)
Q: 結局、サステナビリティを重視するならどのプラットフォームが一番おすすめですか?
A: 一概に「一番」を決めるのは困難です。例えば、物流全体の効率化や品質管理による廃棄削減を重視するならZOZOTOWNのBtoCモデルに分があります。一方で、身近なコミュニティ内でモノを循環させ、新たな生産を抑制する手軽さを重視するならメルカリやラクマのCtoCモデルが貢献していると言えます。この記事で示した複数の評価軸を参考に、ご自身の価値観に合うプラットフォームを選ぶことが重要です。
Q: 個人間の古着売買(CtoC)で、環境のためにできることはありますか?
A: 梱包材を再利用したり、過剰な包装を避けたりすることがまず挙げられます。また、複数の商品をまとめて発送する「まとめ買い」機能を活用することも、輸送回数を減らしCO2削減に繋がります。さらに、商品の状態を正確に伝え、長く使える衣類を取引することも、持続可能な消費行動の一環です。
Q: ZOZOTOWNの「ブランド古着」は、ファストファッションの古着よりサステナブルですか?
A: 耐久性の高い高品質なブランド古着は、安価なファストファッションに比べて長く着用できる可能性が高く、その点で廃棄物の削減に貢献し、よりサステナブルな選択と言える場合があります。ただし、生産背景や素材によっては一概には言えません。重要なのは、一つの製品をどれだけ長く、大切に使うかという視点です。
Q: 海外ではどのような古着ECプラットフォームが人気ですか?
A: 米国の「thredUP」や高級ブランドに特化した「The RealReal」、欧州の「Vinted」などが代表的です。これらのプラットフォームは、単なる売買の場に留まらず、リペアサービスやスタイリング提案、サステナビリティに関する情報発信などを通じて、循環型ファッションのハブとしての役割を担っています。今後の日本のプラットフォームを占う上で参考になります。
Q: 「ライフサイクルアセスメント(LCA)」とは具体的に何ですか?
A: ライフサイクルアセスメント(Life Cycle Assessment)とは、製品やサービスが原料調達から製造、使用、廃棄、リサイクルに至るまでの一生涯(ライフサイクル)を通じて、環境にどのような影響を与えるかを定量的に評価する手法です。CO2排出量や水消費量などを算出し、環境負荷を客観的に比較・分析するために用いられます。
まとめ
本稿では、国内の主要古着ECプラットフォームであるメルカリ、ZOZOTOWN、ラクマを、「持続可能性」と「将来性」という観点から多角的に分析しました。
- メルカリ: CtoCの雄として、CO2削減量の可視化などデータに基づいたアプローチと「エコシステムの構築」で市場をリードしています。
- ZOZOTOWN: BtoCモデルの強みを活かし、「効率的な衣料品循環ループ」をビジネスに組み込んでいます。
- ラクマ: 楽天経済圏を背景に持ち、「ユーザー参加の促進」による潜在的な可能性を秘めています。
LCAの視点では、物流や品質管理のプロセスにおいてそれぞれに長所と課題が見られました。今後の勝敗を分けるのは、テクノロジーの活用、一次流通との連携、そして国際的な規制動向への対応力でしょう。
最終的にどのプラットフォームを選ぶべきか、その答えは一つではありません。この記事が、読者の皆様一人ひとりが自身の消費行動を見つめ直し、より持続可能なファッションの未来に参加するための判断材料となることを、心から願っています。