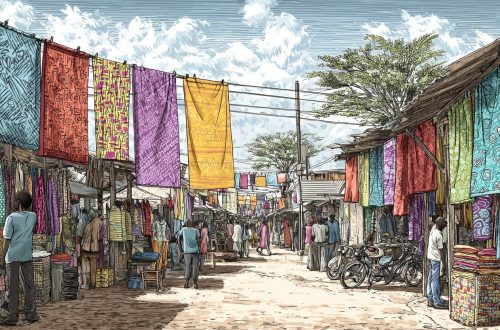執筆者:田中 美穂(株式会社サステナブル・ファッション・ラボ 代表取締役 / 早稲田大学商学学術院 客員研究員)
近年、サステナビリティへの関心とZ世代の台頭を背景に、ファッションリユース市場は驚異的な成長を遂げています。その中心にいるのが、世界最大級のオンライン委託販売プラットフォーム「thredUP」です。2021年のIPOは、リユースビジネスがファッション業界のメインストリームになったことを象徴する出来事でした。しかし、彼らの成功は単なる時流に乗っただけではありません。
本記事では、サステナブルファッション研究者の視点から、thredUPのIPOが持つ意味を紐解き、その成功を支える「テクノロジー」「物流」、そして独自のBtoB戦略「Resale-as-a-Service (RaaS)」を徹底解剖します。データに基づき、彼らが如何にして「一点モノ」というリユースの課題を克服し、巨大なECプラットフォームを築き上げたのか、その本質に迫ります。
🔍 この記事の結論:thredUPのIPOが示した「リユースEC成功の3原則」
| 成功要素 | 内容 |
|---|---|
| 1. テクノロジー主導の最適化 | AIとデータ解析により、膨大な中古アイテムの在庫・価格・配送を自動最適化。効率と利益率を両立。 |
| 2. RaaSモデルの展開 | ブランド向け「Resale-as-a-Service」でBtoBビジネスを拡大。既存ECに“リユース機能”を提供。 |
| 3. サステナビリティ×Z世代の共感 | ESG投資・Z世代の価値観を捉えた“循環型ファッション”戦略で、ブランド価値と投資魅力を両立。 |
👉 本文では、これら3原則がどのようにthredUPのIPO成功と市場拡大を支えたのか、データと事例で詳しく解説します。
目次
なぜ今thredUPなのか?IPOが示したリユース市場の巨大な可能性
2021年IPOの概要と市場の反応
2021年3月、thredUPはNASDAQ市場への上場を果たし、新規株式公開(IPO)によって1億6,800万ドルを調達、評価額は約13億ドルに達しました。このIPOは、先行して上場していたThe RealReal(2019年上場)やPoshmark(2021年1月上場)といった競合の動きに続くものであり、リユースファッションというセクターが、一時的なトレンドではなく、投資対象として確固たる地位を築いたことを市場に示す重要なマイルストーンとなりました。
thredUPのIPOは、単に一企業の資金調達成功に留まりません。これは、サーキュラーエコノミー(循環型経済)を体現するビジネスモデルが、伝統的なファッション業界の線形経済(リニアエコノミー:生産・消費・廃棄)に対するオルタナティブとして、経済的にも成立しうるという力強い証明です。私の専門である国際市場動向の観点から見ても、このIPOは世界中の投資家やファッション関連企業に対し、リユース市場の信頼性と将来の成長期待を劇的に高める起爆剤になったと考えられます。
データで見る世界のファッションリユース市場の成長性
thredUPのIPOが市場から好意的に受け入れられた背景には、リユース市場そのものの圧倒的な成長ポテンシャルがあります。調査会社GlobalDataとの共同レポートによると、世界のファッションリユース市場は2023年に1,970億ドルに達し、2028年には3,500億ドル規模にまで拡大すると予測されています。これは、アパレル市場全体の成長率を大きく上回るペースです。
【図表1:世界のリユース市場規模予測】
| 年 | 市場規模(予測) | 成長率(CAGR) |
|---|---|---|
| 2023年 | 1,970億ドル | – |
| 2028年 | 3,500億ドル | 12% |
| 出典: thredUP “2024 Resale Report” (GlobalData調べ) |
この急成長を牽引しているのが、Z世代やミレニアル世代といった若年層の消費者です。彼らは、価格の手頃さだけでなく、サステナビリティや個性の表現を重視する価値観を持っています。調査によれば、Z世代の約3人に1人がサステナブルファッションを認知しており、その多くが購入経験があることが示されています。この消費者行動の変化は不可逆的であり、リユース市場の持続的な成長を支える基盤となっているのです。
サステナビリティとESG投資の潮流が追い風に
ファッション業界は、長年にわたり大量生産・大量廃棄という構造的な問題を抱え、環境負荷が最も高い産業の一つとして指摘されてきました。国連の報告によれば、ファッション産業は世界の二酸化炭素排出量の10%を占めるとも言われています。
このような状況下で、thredUPのビジネスモデルは、衣類の寿命を延長し廃棄物を削減する直接的な解決策として、ESG(環境・社会・ガバナンス)投資家から高く評価されています。投資家は、thredUPが持つ以下の点に企業価値を見出していると考えられます。
- 環境(E): 衣類廃棄量の削減、新品生産に伴うCO2排出量・水使用量の抑制といった、定量化可能な環境負荷削減効果。
- 社会(S): 消費者に対して、手頃な価格でサステナブルな消費行動を実践する選択肢を提供。
- ガバナンス(G): テクノロジーを活用した透明性の高いサプライチェーンとビジネスモデルの構築。
thredUPのIPOは、環境価値と経済価値がトレードオフの関係ではなく、両立しうることを示しました。これは、サステナビリティを経営の中核に据えることが、長期的な企業価値向上に繋がるという現代のESG投資の潮流を象徴する事例と言えるでしょう。
thredUP成功戦略の核心:3つの柱を徹底解剖
thredUPの成功は、単に市場の追い風に乗っただけではありません。彼らは「一点モノ」という中古品の特性がもたらす複雑性を、テクノロジーと独自の仕組みによって克服し、圧倒的な競争優位性を築いています。その核心は、以下の3つの柱に集約されます。
1. テクノロジーとデータが支える「一点モノ」の効率的な商品化
リユースビジネスにおける最大の課題は、一点ずつ状態もブランドも異なる商品を、いかに効率的に処理し、商品化するかという点です。thredUPは、この課題を解決するために、テクノロジーとデータ活用へ巨額の投資を行ってきました。
彼らの巨大な物流センターでは、毎日10万点以上ものアイテムが処理されています。そのプロセスは高度に自動化・システム化されています。
- AIによる査定・価格設定: 到着した衣類は、AIの画像認識技術によってブランドやアイテムカテゴリが特定され、過去の膨大な販売データに基づいて最適な販売価格が自動で設定されます。これにより、属人的な判断を排し、迅速かつ収益性の高い価格設定を実現しています。
- 自動撮影・採寸: 各アイテムは自動化されたステーションで撮影され、AIが色や柄、さらにはサイズまで自動で検出・採寸することさえ可能になっています。
- パーソナライズされたEC体験: 膨大なSKU(在庫管理単位)の中から、顧客一人ひとりの好みや購買履歴に基づいた商品を推薦するアルゴリズムを構築。これにより、顧客は宝探しのような体験を楽しみながら、欲しいものに効率的に出会うことができます。
これらのテクノロジーは、従来の古着屋や、出品者が自身で撮影・値付け・発送を行うCtoCフリマアプリに対する明確な優位性となっています。
2. 圧倒的な利便性を生む独自の物流システム「クリーンアウトキット」
質の高い在庫を、いかに安定的かつ大量に集めるか。これはリユース事業の生命線です。thredUPはこの課題に対し、「クリーンアウトキット」という画期的なソリューションを提示しました。
これは、売り手が専用の袋に不要な衣類を詰めて送るだけで、あとの査定、撮影、出品、保管、発送といった全てのプロセスをthredUPが代行する仕組みです。消費者行動分析の観点から見ると、これは衣類を売りたい人が感じる「面倒くさい」「時間がない」といった最大のペイン(悩み)を解消する、極めて優れたモデルです。
この「売り手」の利便性を徹底的に追求したことで、thredUPは家庭に眠る良質な衣類を継続的に集めることに成功しています。彼らが運営する複数の巨大な物流センターは、合計で数百万点以上を保管できる規模を誇り、このモデルを物理的に支えるインフラとなっています。
3. 業界のゲームチェンジャー「Resale-as-a-Service (RaaS)」
thredUPの戦略で最も注目すべきは、BtoB事業である「Resale-as-a-Service(RaaS)」です。これは、thredUPがこれまで培ってきた物流インフラ、テクノロジー、査定ノウハウをパッケージ化し、他のブランドや小売業者にプラットフォームとして提供するサービスです。
パートナー企業は、RaaSを利用することで、自社のウェブサイトや店舗で、顧客から不要になった自社製品を回収したり、中古品を販売したりするリユースプログラムを低リスクかつ迅速に開始できます。
コンサルタントとしての視点からこの戦略を考察すると、その意図は極めて多層的です。
- 市場全体のパイ拡大: 競合他社を「顧客」に変え、リユース市場全体の成長を加速させる。
- 高品質な在庫の確保: パートナーブランドを通じて、質の高いブランドアイテムを優先的に確保する。
- データ収集の強化: パートナー企業との連携により、新品市場のデータや顧客動向も把握し、自社の価格設定や需要予測の精度をさらに向上させる。
- 業界標準(デファクトスタンダード)の確立: リユース事業の「OS(オペレーティングシステム)」となることで、業界内での不可欠な存在を目指す。
RaaSは、thredUPを単なる一EC企業から、ファッション業界全体のサーキュラーエコノミー移行を支えるインフラ企業へと変貌させる可能性を秘めた、非常に野心的な戦略であると言えます。
サーキュラーエコノミーの観点から分析するthredUPの企業価値
「所有」から「利用」へ:ファッションの循環を加速させるプラットフォーム
thredUPのビジネスは、サーキュラーエコノミーの基本原則である「製品と原料の価値を可能な限り長く維持し、廃棄物をなくす」という考え方を具現化したものです。彼らは、一度市場に出た衣類を再び循環させることで、そのライフサイクルを劇的に延長させています。
私の専門であるマテリアルフロー(物質循環)の観点から評価すると、thredUPはファッション業界における物質の流れを、一方通行の「線形」から循環型の「円環」へと転換させるための重要な結節点(ノード)としての役割を担っています。彼らのプラットフォームが巨大化すればするほど、新品の生産に投入される資源量が抑制され、同時に廃棄される衣類の量が削減されるため、業界全体の環境負荷低減に大きく貢献すると考えられます。
ライフサイクルアセスメント(LCA)で見る環境負荷削減効果
thredUPのビジネスが持つ環境価値は、ライフサイクルアセスメント(LCA)という手法を用いることで、より客観的かつ定量的に評価することが可能です。LCAは、製品やサービスがその生涯(原料調達から製造、使用、廃棄・リサイクルまで)を通じて環境に与える影響を評価する手法です。
具体的な研究によれば、中古品を1点購入することは、新品の製造と比較して環境負荷を大幅に削減できることが示唆されています。thredUP自身の試算では、中古品を1点購入することで、新品と比較して平均でCO2排出量を25%削減できるとしています。また、ある研究では、綿のTシャツ1枚を生産するには約2,700リットルの水が必要であると指摘されており、中古品の利用が水資源の保全に繋がることも明らかです。
【表2:中古品購入による環境負荷削減効果(概念図)】
| 環境負荷項目 | 新品生産 | 中古品購入 | 削減効果 |
|---|---|---|---|
| CO2排出量 | 高 | 低 | 大 |
| 水使用量 | 高 | 低 | 大 |
| 廃棄物量 | 発生 | 抑制 | 大 |
これらのデータは、thredUPのプラットフォームが拡大することが、地球環境にとって直接的なプラスの影響をもたらすことを示唆しています。
RaaSがもたらす業界全体のサステナビリティ変革
前述のRaaS戦略は、サーキュラーエコノミーの観点からも極めて重要な意味を持ちます。RaaSを通じて、これまで大量生産・大量販売を前提としてきた多くのファッションブランドが、自社のビジネスモデルに「リユース」という循環の仕組みを組み込むことが可能になります。
これは、thredUP一社の取り組みが、業界全体の構造変革を促す触媒として機能していることを意味します。彼らは自社の利益追求だけでなく、他のステークホルダー(利害関係者)を巻き込みながら、ファッション業界全体のサステナビリティ移行を加速させる「OS(オペレーティングシステム)」としての役割を担いつつあるのです。このエコシステム全体をデザインする視点こそ、thredUPの企業価値の根幹にあると私は分析しています。
日本のリユースECがthredUPから学ぶべきこと
CtoCフリマアプリとの差別化戦略
日本のリユース市場は、メルカリに代表されるCtoC(個人間取引)のフリマアプリが主流です。これは手軽さという点で非常に優れていますが、一方で「出品の手間」「品質のばらつき」「個人間トラブル」といった課題も内包しています。
thredUPの「CtoBtoC(委託販売)」モデルは、まさにこれらの課題に対するソリューションを提供しています。
- 品質管理: 専門スタッフによる検品・査定が行われるため、購入者は安心して商品を選ぶことができます。
- 手間削減: 売り手は箱に詰めて送るだけであり、出品に関する一切の手間から解放されます。
日本の事業者も、単なる価格競争に陥るのではなく、thredUPのように「品質保証」や「利便性」といった付加価値を提供することで、CtoCプラットフォームとの明確な差別化を図ることが可能であると考えられます。特に、ジャパンクオリティを求める消費者の要求水準は高く、信頼性の高い品質管理体制の確立は、サステナブルファッションにおいて極めて重要な要素です。
「売り手」の体験価値向上への投資の重要性
thredUPの成功の鍵は、購入者(買い手)だけでなく、「売り手」の体験価値を徹底的に追求した点にあります。日本では「買い手は神様」という言葉がありますが、リユースビジネスにおいては「売り手も神様」なのです。良質な商品を安定的に確保するためには、売り手にとって魅力的で、手間がなく、信頼できるサービスを提供し続ける必要があります。
日本の事業者が今後、質の高い商品を安定的に確保するためには、以下のような売り手向けサービスの構築が重要となるでしょう。
- シームレスな集荷サービス: 自宅から一歩も出ずに商品を発送できる仕組みの提供。
- 迅速で透明性の高い査定プロセス: 査定状況がリアルタイムでわかり、納得感のある価格が提示される仕組み。
- 多様な対価の提供: 現金だけでなく、提携ブランドで使えるクーポンやポイントなど、売り手のライフスタイルに合わせたインセンティブの設計。
BtoB(RaaS)展開による新たな成長機会
日本でも、アパレル企業が自社製品のリユースやサステナビリティへの取り組みに関心を持ち始めています。この動きは、thredUPのRaaSモデルを日本市場に応用する大きなチャンスを示唆しています。
例えば、以下のような事業モデルが考えられます。
- アパレルブランド向けRaaS: ブランドの公式ECサイトにリユース機能を統合し、顧客ロイヤルティ向上と新たな収益源を創出する。
- 商業施設との連携: 商業施設内に「クリーンアウトキット」の回収拠点を設け、施設全体の送客とサステナブルなイメージ向上に貢献する。
- 異業種連携: クリーニング業界や物流業界と連携し、検品・メンテナンス・保管・配送の各プロセスを最適化する。効率的な物流設計により、環境負荷とコストの両面で最適化を実現している事例は、大いに参考になります。
これらのBtoB展開は、単独のEC事業に比べて安定した収益基盤を築きやすく、業界全体を巻き込むことでより大きなインパクトを生み出す可能性を秘めています。
よくある質問(FAQ)
Q: thredUPのビジネスモデルは儲かるのですか? なぜ赤字が続いているのですか?
A: thredUPは委託販売した商品の販売手数料で収益を得ています。手数料率は商品の価格帯によって変動します。現在赤字が続いている主な理由は、巨大な物流センターの構築やテクノロジー開発への先行投資が大きいためです。これは、将来の市場シェアを確立するための戦略的投資と捉えられており、売上自体は成長を続けています。
Q: thredUPと日本のメルカリとの最大の違いは何ですか?
A: 最大の違いは取引形態です。メルカリは個人間が直接売買する「CtoC」であるのに対し、thredUPは商品を一度預かり、検品・撮影・出品・発送までを代行する「CtoBtoC(委託販売)」モデルです。これにより、買い手は品質の担保、売り手は出品の手間削減というメリットを享受できます。
Q: thredUPの「Resale-as-a-Service (RaaS)」とは具体的にどのようなサービスですか?
A: RaaSは、他のファッションブランドや小売業者が、自社のウェブサイトや店舗で簡単にリユースプログラムを導入できるプラットフォームサービスです。thredUPが持つ物流網や査定ノウハウ、EC技術をパッケージで提供することで、パートナー企業は低リスクで循環型ビジネスに参入できます。
Q: なぜZ世代はthredUPのようなリユースサービスを支持するのですか?
A: 消費者行動分析の観点から、Z世代は価格の安さだけでなく、環境への配慮や個性の表現を重視する傾向があります。thredUPは、サステナブルな消費を手軽に実践できる点、そして膨大な商品の中から自分だけのユニークなアイテムを見つけられる点で、彼らの価値観に強く合致していると考えられます。
Q: 日本の企業がthredUPのモデルを導入する上での課題は何ですか?
A: 日本の住宅事情(保管スペースの狭さ)や消費者の品質に対する要求の高さが挙げられます。また、thredUPのような大規模な物流・検品センターを構築するための初期投資も大きな課題です。まずは特定のブランドやカテゴリに特化するなど、スモールスタートでの展開が現実的かもしれません。
まとめ
本記事では、米国リユース最大手thredUPのIPOを起点に、その巨大ECプラットフォームの成功戦略を、サステナブルファッション研究者の視点から多角的に分析しました。thredUPの強さは、単にリユース市場の成長に乗っただけでなく、テクノロジーと物流への巨額投資によって「一点モノ」を効率的に扱う仕組みを構築し、売り手の利便性を極限まで高めた点にあります。
さらに、業界全体を巻き込む「RaaS」戦略は、彼らを単なるECプラットフォームから、サーキュラーファッション経済のOSへと昇華させる可能性を秘めています。日本のリユース市場も大きな転換期を迎えています。thredUPの事例は、環境価値と経済価値を両立させるビジネスモデルの構築を目指す全ての日本企業にとって、極めて重要な示唆を与えてくれるはずです。持続可能な未来のファッションを創造するための第一歩を、共に踏み出しましょう。