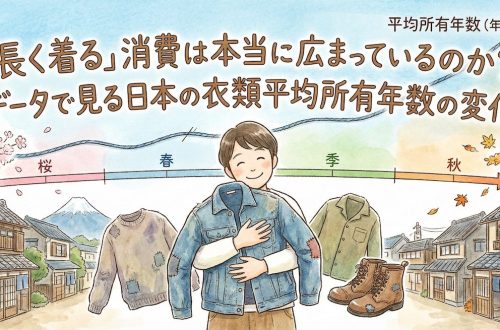執筆者:田中 美穂(株式会社サステナブル・ファッション・ラボ 代表取締役 / 早稲田大学商学学術院 客員研究員)
近年、Z世代を中心にファッション市場で古着ブームが加速しています。その背景には「他人と被らない、自分だけのスタイル」を求める価値観があり、しばしば「古着は一点物だから」という言葉で象徴されます。しかし、この「一点物」という価値観は、果たして本質的な真実なのでしょうか。
本稿では、サステナブルファッション研究の第一人者として、国内外の市場と消費者行動を分析してきた専門家の視点から、この問いを深掘りします。統計データとサーキュラーエコノミーの理論を基に、Z世代が古着に熱狂する深層心理と、現代のファッション業界が直面する構造的変化について、多角的に考察します。
【この記事の結論】Z世代が古着に熱狂する3つの深層心理
- 自己表現と希少性への欲求
ファストファッションが主流の時代に育ったため、「他人と被らない」という価値を重視。古着を個性的なスタイルを確立するためのツールと捉えている。- サステナビリティ(持続可能性)への意識
ファッション業界の環境負荷を認識しており、罪悪感なくおしゃれを楽しめる倫理的な選択肢として古着を選んでいる。これは「ごめんね消費」を避ける行動でもある。- 新しい消費価値観(ホッピング消費)
商品を長く「所有」するのではなく、フリマアプリでの再販を前提に一時的に「利用」するスタイル。古着の売買は、この循環プロセスを楽しむ価値観と一致している。
目次
Z世代の古着ブームをデータで読み解く:市場規模と消費行動の変化
Z世代の古着ブームは、単なる感覚的なトレンドではなく、明確なデータによって裏付けられています。市場の構造的変化と彼ら特有の消費行動を分析することで、その本質が見えてきます。
日本国内リユース市場の拡大とZ世代の寄与
まず、マクロな視点から市場規模を確認します。リユース経済新聞社の調査によると、2023年の国内リユース市場規模は前年比7.8%増の約3.1兆円に達し、14年連続で拡大しています。 中でも「衣料・服飾品」は主要カテゴリーの一つであり、市場全体の成長を牽引しています。
この成長の背景には、Z世代の積極的な参加が挙げられます。株式会社メルカリが2024年に行った調査では、Z世代の71.1%が直近1年間で中古品の購入経験があると回答し、全体(56.8%)を大きく上回りました。 彼らは中古品への心理的抵抗が極めて低く、リユース市場の主要なステークホルダーとなりつつあることが示唆されています。
「所有」から「利用」へ:ホッピング消費という新たな価値観
Z世代の消費行動で特筆すべきは、「ホッピング消費」と呼ばれるスタイルです。これは、商品を長く所有することを前提とせず、一度利用した後にフリマアプリなどで再販することを前提に購入する消費行動を指します。
この価値観は、一つのアイテムを「所有」することから、一時的に「利用」し、次のユーザーへ循環させるという、サーキュラーエコノミーの考え方と非常に親和性が高いと言えます。彼らにとって衣服は資産の一部であり、流動性の高いファッションアイテムを循環させるプロセス自体を楽しむ傾向が見られます。この行動様式が、古着を購入し、再び手放すことへのハードルを著しく下げていると考えられます。
SNSが加速させる「自分らしさ」の探求と古着の役割
デジタルネイティブであるZ世代にとって、SNSは単なるコミュニケーションツールではなく、自己を表現し、アイデンティティを確立するための重要なプラットフォームです。SHIBUYA109 lab.の調査では、Z世代がファッションを「相手との関係性をより彩るツール」として活用している実態が報告されています。
画一的になりがちなファストファッションに対し、古着は「他人と被らない」という強力な価値を提供します。 SNS上で自身のユニークなスタイリングを披露することが自己表現の重要な手段となる中で、古着は個性的なスタイルを構築するための不可欠なツールとして機能しているのです。この「自分らしさ」への強い欲求が、古着市場の需要を根底から支えていると言えるでしょう。
「古着=一点物」は本当か?市場構造から見る価値の真実
Z世代を惹きつける「一点物」という言葉。しかし、専門家の視点から市場を俯瞰すると、その言葉が持つ意味は一様ではないことがわかります。
「一点物」の定義:ヴィンテージ、ユーズド、ベール品の階層構造
一般に「古着」と総称される市場は、実際には価値の異なる複数の階層から成り立っています。この構造を理解することが、「一点物」の真実を解き明かす鍵となります。
- ヴィンテージ (Vintage)
- 定義: 製造から数十年以上が経過し、歴史的・文化的価値が認められた希少なアイテムを指します。 明確な定義はありませんが、一般的に30年以上前のものが目安とされることが多いようです。
- 特徴: 当時の製法やデザイン、素材が再現不可能である場合が多く、コレクターズアイテムとしての側面も持ちます。これらは真の意味での「一点物」に近い存在と言えるでしょう。
- ユーズド (Used)
- 定義: 単に一度使用された中古衣料全般を指します。 比較的新しい年代のブランド古着からノーブランド品まで、幅広く含まれます。
- 特徴: 市場に流通している古着の大半がこれに該当します。同じ商品が複数存在することもあり、厳密な意味での「一点物」とは言えないケースも少なくありません。
- ベール品 (Bale)
- 定義: 海外から輸入される、圧縮梱包された古着の塊を指します。これらは重量単位で取引され、開封されるまで中身は分かりません。
- 特徴: 低価格帯の古着店の商品ソースとなることが多く、中には同じデザインのTシャツなどが複数含まれていることもあります。これらは「一点物」とは対極にある、大量流通品としての側面を持ちます。
こうした古着の供給源は世界中にありますが、特に東南アジア、中でもタイは世界有数の古着集積地として知られています。
プロのバイヤーがどのように現地で買い付けを行うかについては、こちらの「タイ古着買い付け完全ガイド|バンコクのおすすめ市場から仕入れの注意点・輸送方法まで徹底解説」で詳しく解説されており、古着のサプライチェーンのリアルな一面を知る上で非常に参考になります。
このように、「古着=一点物」という認識は、必ずしも市場の現実を正確に反映しているわけではないのです。
なぜZ世代は「一点物」という言葉に惹かれるのか?
では、なぜZ世代はこの言葉に強く惹きつけられるのでしょうか。これは、彼らが育った時代背景と深く関連していると考えられます。
大量生産・大量消費のファストファッションが当たり前の環境で育った彼らにとって、「一点物」という言葉は、単なる希少性以上の情緒的価値を持ちます。それは「偶然の出会い」や、服が持つ「物語性(ナラティブ)」への憧憬です。無限の選択肢が提示されるデジタル社会において、偶然性やセレンディピティ(素敵な偶然に出会う能力)が、かえって新鮮で魅力的に映るのです。この消費行動は、機能的価値(モノ)や体験価値(コト)を超えた、「エモ消費」や「イミ消費」といった新しい価値観の潮流とも合致しています。
マーケティングとしての「一点物」と消費者の賢い選択
古着店にとって「一点物」は、消費者の購買意欲を刺激する強力なマーケティングワードです。この言葉は、「今、ここで買わなければ二度と手に入らないかもしれない」という切迫感を生み出し、購買決定を後押しします。
しかし、賢い消費者としては、その言葉の裏にある市場構造を理解することが重要です。私が提言したいのは、「一点物」という言葉の魅力に囚われるだけでなく、その衣服が持つ本質的な価値を見極める視点を持つことです。
- 品質の評価: 縫製の質、生地の耐久性、デザインの普遍性など。
- 背景の理解: ブランドの歴史、製造された年代の文化など。
- 自身の価値観との接続: その服が本当に自分のスタイルや哲学に合っているか。
これらの視点を持つことで、マーケティングに流されることなく、真に価値のある一着と出会うことができるでしょう。
サステナビリティという必然:Z世代の環境意識とファッションの未来
Z世代の古着ブームを語る上で、サステナビリティへの意識は不可欠な要素です。彼らの行動は、ファッション業界の未来を占う重要な指標と言えます。
環境負荷への意識と「ごめんね消費」のジレンマ
各種調査で、Z世代の環境問題への関心の高さは一貫して示されています。 パナソニックの調査では、Z世代の82.5%がサステナブルな製品の導入意向があると回答しています。 ファッション産業が環境に大きな負荷を与えているという認識は、彼らの間で広く共有されています。
しかし、その一方で、安価でトレンド性の高いファストファッションの魅力も依然として強力です。この理想と現実の狭間で、「環境に悪いと知りながらも、安さやデザインに惹かれてファストファッションを買ってしまい、罪悪感を覚える」という、いわゆる「ごめんね消費」とも呼べる心理状態が生まれています。
古着を選ぶという行為は、このジレンマに対する明確な解決策の一つとして機能しています。新たな資源を使わずにファッションを楽しむことができる古着は、彼らにとって環境への配慮と自己表現を両立させる、合理的かつ倫理的な選択肢なのです。
サーキュラーエコノミーの担い手としてのZ世代
私の専門分野であるサーキュラーエコノミー(循環型経済)は、「作って、使って、捨てる」という従来のリニアエコノミー(直線型経済)から脱却し、資源を循環させ続ける経済システムです。
Z世代がフリマアプリなどを通じて古着を売買する行為は、彼らが意識しているか否かに関わらず、まさにサーキュラーエコノミーを実践していることに他なりません。彼らは、消費者であると同時に、循環システムの重要な供給者・担い手でもあるのです。この世代が経済活動の中心となる未来において、リユースを前提としたビジネスモデルは、あらゆる業界で標準になっていく可能性が高いと考えられます。
国際比較:世界のZ世代はサステナビリティをどう捉えているか
国際的な視点で見ると、サステナビリティへのアプローチには地域差が見られます。例えば欧州では、消費者個人の意識だけでなく、政策レベルでの取り組みが強力に推進されています。欧州委員会が発表した「持続可能で循環型の繊維製品に関するEU戦略」では、製品の長寿命化やリサイクル性の向上、売れ残り品の廃棄禁止などが盛り込まれ、「修理する権利」の法制化も進んでいます。
これに対し、日本のZ世代の古着ブームは、政策主導というよりも、カルチャーや自己表現、経済合理性といった内発的な動機から発生している側面が強いのが特徴です。 しかし、この日本独自のムーブメントは、結果として世界的なサーキュラーエコノミーへの移行に貢献する大きなポテンシャルを秘めていると言えるでしょう。
提言:これからのファッションと私たちの向き合い方
Z世代の古着ブームが示す潮流を踏まえ、これからのファッション業界と私たち消費者はどうあるべきか。専門家として3つの視点から提言します。
1. 「一点物」の価値観を超えて:本質的な価値の見極め方
「一点物」という言葉の情緒的な魅力は認めつつも、私たちはより本質的な価値基準を持つ必要があります。ここで重要になるのが、ライフサイクルアセスメント(LCA)の考え方です。LCAとは、製品の原料調達から製造、使用、廃棄に至るまでの全段階における環境負荷を定量的に評価する手法です。
全ての消費者がLCAを計算する必要はありませんが、その考え方を意識することは可能です。
- 素材: 環境負荷の低い素材か、リサイクル素材か。
- 製造: サプライチェーンは透明か、労働環境は公正か。
- 耐久性: 長く使えるデザインと品質か。
- 修繕可能性: 修理して使い続けることができるか。
一着を長く大切に着ることこそが、最もサステナブルな行動です。この視点が、真に価値ある服を選ぶための羅針盤となります。
2. 企業に求められる透明性と循環型ビジネスモデルへの転換
消費者だけでなく、アパレル企業側の変革は急務です。サプライチェーンの透明性を確保し、どこで、誰が、どのように作っているのかを消費者に開示するトレーサビリティの構築が不可欠です。
さらに、リペア(修繕)、リセール(再販)、レンタルといった、サーキュラーエコノミーに基づいた新しいビジネスモデルへの転換が求められます。国内外で先進的な取り組みは既に始まっており、これらはもはやCSR(企業の社会的責任)活動ではなく、事業成長の核となるべき領域です。特に、サプライチェーン全体の最適化は不可欠です。
例えば、アジア諸国でリユース品を効率的に循環させる際には、現地での厳格な品質管理体制が成功の鍵となります。ジャパンクオリティを海外で実現し、効率的な物流設計によって環境負荷とコストの最適化を両立させている企業の取り組みは、業界全体の品質基準を引き上げる上で重要な示唆を与えています。
3. 私たち一人ひとりができること:賢い消費者から責任ある市民へ
最後に、私たち一人ひとりが日々の生活で実践できるアクションを提案します。
- 長く着る: 手持ちの服を最大限活用し、安易な買い替えを控える。
- 修理する: ほつれやボタンの取れは、自分で、あるいは専門店で修理する。
- 賢く選ぶ: 購入する際は、背景にあるストーリーや環境負荷を考慮する。
- 適切に手放す: 不要になった服は、ごみとしてではなく、資源としてリユースやリサイクルに出す。
これらの行動は、単なる「賢い消費者」としての振る舞いを超え、持続可能な社会の実現に貢献する「責任ある市民」としてのアクションです。ファッションは、そのための最も身近でパワフルなツールとなり得ます。
よくある質問(FAQ)
Q: Z世代が古着を好きな一番の理由は何ですか?
A: 一つの理由に絞ることは難しいですが、主な要因として「自己表現欲求」「経済合理性」「環境意識」の3つが複雑に絡み合っていると考えられます。ファストファッションでは得られない個性的なデザインを、手頃な価格で、かつ環境負荷を抑えながら手に入れられる点が、Z世代の価値観に強く響いています。
Q: 「ヴィンテージ」と普通の古着の違いは何ですか?
A: 一般的に「ヴィンテージ」は、製造から数十年以上が経過し、歴史的・文化的価値が認められた特定のアイテムを指します。 一方、「古着(ユーズド)」は単に一度使用された衣類全般を指します。ヴィンテージは希少性が高く、コレクターズアイテムとしての側面も持ちますが、すべての古着がそうであるわけではありません。
Q: 古着は本当に環境に優しいのでしょうか?
A: はい、新たな資源やエネルギーを使わずに既存の衣類を再利用する点で、新品の服を生産するよりも環境負荷は大幅に低いと言えます。これはサーキュラーエコノミーの観点からも非常に重要です。ただし、古着の輸送やクリーニングでエネルギーは消費されるため、購入した一着を長く大切に着ることが最もサステナブルな行動と言えるでしょう。
Q: 古着を買うときに気をつけるべきことはありますか?
A: 状態の確認が最も重要です。シミ、ほつれ、虫食いなどがないかを細かくチェックしましょう。また、ブランド古着の場合は偽物の可能性もゼロではありません。信頼できる店舗で購入することをお勧めします。サイズ感も現代の服とは異なる場合が多いため、必ず試着することが失敗しないコツです。
Q: 古着ブームは今後も続きますか?
A: 一時的なトレンドとしての熱狂は落ち着く可能性がありますが、リユース市場自体は今後も拡大が予測されています。 特にサステナビリティや個性を重視する価値観はZ世代以降にも引き継がれると考えられるため、古着はファッションの選択肢として定着していくと専門家は見ています。
まとめ
Z世代が古着に熱狂する背景には、「一点物」という言葉に象徴される自己表現への渇望があります。しかし、その深層を分析すると、単なる懐古主義や個性派志向に留まらない、より構造的な社会変化が見えてきます。
本稿で考察したように、「一点物」という価値観は、市場の現実とマーケティング戦略が絡み合った多面的な概念です。Z世代は、この言葉をフックとしながらも、無意識のうちにサステナビリティやサーキュラーエコノミーを実践し、新しい消費の形を模索しています。彼らの行動は、大量生産・大量消費を前提としてきたファッション業界に対し、本質的な価値とは何か、そして持続可能な未来とは何かを問い直す、力強いメッセージと言えるでしょう。
私たち一人ひとりがこの問いに向き合い、賢明な選択を重ねることが、未来のファッションをより豊かにしていく鍵となります。